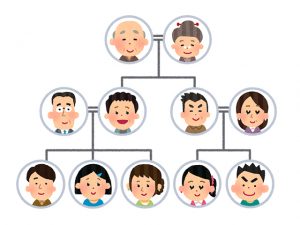お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
世界の偉人のお墓 浮世絵師編〜東洲斎写楽〜
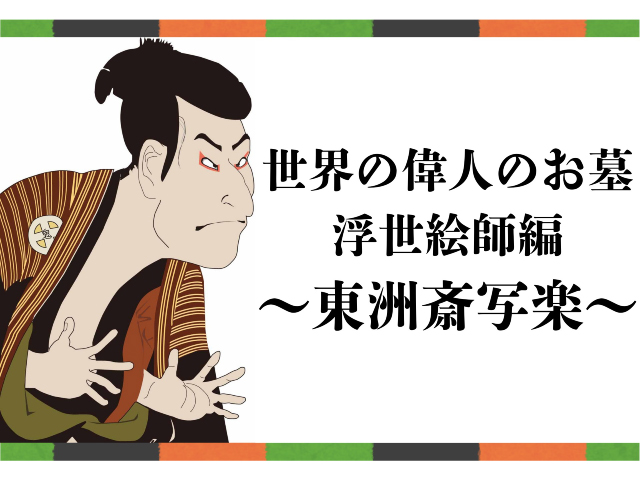
近頃は、有名人や偉人のお墓巡りを趣味にしている人々を「墓マイラー」と呼び、秘かなブームにもなっています。はたしてドラマや映画、書籍などで見た偉人たちは、どのような生涯を送り、どこの地で永遠の眠りについているのでしょうか。偉人たちの伝説的エピソードに触れながら、終の棲家にも想いを巡らせてみてはいかがでしょう。
今回は「浮世絵師編~東洲斎写楽~」(以下、写楽)と題して、写楽の人物像とお墓についてお伝えします。
1794年5月に28枚もの作品を発表して鮮烈デビューを飾った写楽は、140点余りの作品を世に残し、10か月後には突如姿を消した「謎の浮世絵師」として強烈なインパクトを残す人物です。
当初は、賛否両論だった写楽の画風ですが、現在は、日本を代表する浮世絵師として高く評価され「四大浮世絵師」の一人になっています。
東洲斎写楽とは
多くの謎に包まれた写楽の人物像を紐解いていきましょう。
東洲斎写楽のプロフィール
写楽が浮世絵師として表舞台に立つまでの生まれや経歴は、何一つ分かっていません。
浮世絵界への鮮烈デビューで発表した大首絵は、江戸三座の控櫓(ひかえやぐら)だった都座・桐座・河原崎座の役者絵でした。これは、黒雲母摺(くろきらずり)という背景に雲母を混ぜた顔料で描かれた大首絵で『市川鰕蔵の竹村定之進』などが代表作です。
ほかにも『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』(さんだいめ おおたにおにじの やっこえどべえ)で、大胆かつ個性的な表現と美醜を問わず個性を強調する写楽の画風は、当時の江戸に衝撃を与えました。
というのも、当時の役者絵は、今で言うポスターのような役割でした。そのため、理想像として美化された表情で描かれることが多く、どの絵も同じような顔つきだったのです。
しかし、写楽は、老いや醜さなど役者の素顔をありのままにとらえ、その演技の特徴までもリアルに描写したため、賛否両論を巻き起こしました。
写楽鮮烈デビューの立役者となったのは、今で言う出版元の蔦屋重三郎。これ以降も突如として姿を消す1795年3月までの全作品を蔦屋重三郎のもとから発表しています。
10か月間という短い浮世絵師の幕を閉じた写楽ですが、姿を消した理由も、その後の人生も、はたまた”そもそも写楽は何者だったのか”も分からないまま、いなくなったのです。
姿を消す直前の写楽は、春狂言10枚や相撲絵2枚などを描いています。華々しくデビューした写楽でしたが、活動後半期は、急速に画力が衰え、質が悪くなり悪評が増えていったと言われます。
人気が急速に下火になった写楽でしたが、明治後期から大正にかけて、海外で再評価されたことで日本でも逆輸入のように再び注目を集めることとなりました。
短い活動期間、突然の失踪、その後の評価の変遷が、写楽の謎を深めていると言えるでしょう。
東洲斎写楽が謎と言われる理由
写楽の存在は、現在でも研究者がいるほど、多くの謎に包まれています。
写楽とは何者だったのか。
現在、最も有力な説は、1763年に生まれた能役者の斎藤十郎兵衛だったという説です。
江戸時代の浮世絵師たちの伝記や作品について詳しく書かれた本「増補浮世絵類考」には「東洲斎写楽」の項目で「俗名は斎藤十郎兵衛、八丁堀(現在の東京都中央区)に住む阿波徳島藩主・蜂須賀家お抱えの能役者である」と記されています。この記述は、斎藤十郎兵衛説を裏付ける重要な証拠の一つと言えるでしょう。
さらには、写楽の活動期間と斎藤十郎兵衛の非番期間が一致していることも、この説を有力なものにしているようです。
非番とは、大名お抱えの能役者が舞台に立たないことを指しており、当時は半年〜1年ほどの非番期間がありました。写楽こと斎藤十郎兵衛は、この期間に浮世絵制作を行ったのではないかと推測されています。
ただし、決定的な証拠はまだ発見されておらず、同時代の他の浮世絵師(葛飾北斎、喜多川歌麿)の別名説、浮世絵以外の絵師(円山応挙、谷文晁)説や中には、版元の蔦屋重三郎が浮世絵師として活動していたのではないかなどの説もあり、完全に解明されたわけではありません。
東洲斎写楽のお墓

出生も、亡くなった時期も分からない写楽は、どこの地で永遠の眠りについているのかも明らかになっていません。現在ある2つの説をもとに、お墓をご紹介します。
1つめは、徳島県徳島市寺町にある東光寺の墓地です。
斎藤十郎兵衛の戒名が記されているお墓があることから、写楽のお墓だとされていますが、真相は分からないままとなっています。
2つめは、埼玉県越谷市の法光寺です。1997年に斎藤十郎兵衛の過去帳が発見されたことで写楽のお墓説の脚光を浴びました。
過去帳には「八丁堀の地蔵橋に住んでいた阿州(あわ)藩の家臣、斎藤十郎兵衛が亡くなりました。享年58歳。千住で火葬されました。」と記されているそうです。
まとめ
今回は、写楽のお墓の場所と人物像を紐解くエピソードを紹介しました。
写楽の作品は、背景を簡略化し、役者の姿を大きく描き出すことで、それまでの浮世絵には見られなかった、リアルかつ今にも動き出しそうな役者絵を生み出しました。
役者の喜怒哀楽が克明に表現されており、まるで生きているかのように躍動感あふれる作品は、後世でも観る者の心を捉えて離しません。
しかし、写楽の素性は、全てが謎に包まれており、確かなことはほとんど分かっていません。
そこで、資料を調べながら、実際に現地に赴き自分の目や耳で見聞きし、ルーツを探って「写楽とは何者なのか?」自分なりに仮説をたてていくのも面白いのではないでしょうか。
偉人のルーツを探るのも面白いものですが、自分の生まれたルーツについても家系図を作るなどして、たどってみると、思いがけないつながりを発見できるかもしれません。
年末の長いお休みにぜひ、自分の祖先、ひいては過去から受け継ぐ命のつながりをたどってみてはどうでしょう。
◆家系図の作り方は?自分で作る方法を解説
また、写楽のお墓参りで四国に行った際は、近県の愛媛まで足を延ばして重要文化財を巡ってみるのもいいでしょう。
◆一度は見ておきたい重要文化財シリーズ・愛媛の旅編
東洲斎写楽のお墓への交通アクセス
東光寺(徳島県)
<鉄道> JR高徳線 徳島駅から徒歩約15分
<バス> 徳島駅から西大工町二丁目で下車後、徒歩約5分
<車> 徳島駅から国道192号または国道318号で約5分
法光寺(埼玉県)
<鉄道> 東武スカイツリーライン「せんげん台駅西口」から徒歩約20分
<バス> 東武スカイツリーライン「せんげん台駅西口」から「獨協埼玉中学・高校」で下車後、徒歩約5分
<車> 国道4号線「陸橋入口」交差点から約5分
東北自動車道「岩槻I.C」から約15分
東北自動車道「浦和I.C」から約30分