お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
弘法大師・空海は何をした人?空海の誕生を祝う「弘法大師降誕会」とは?
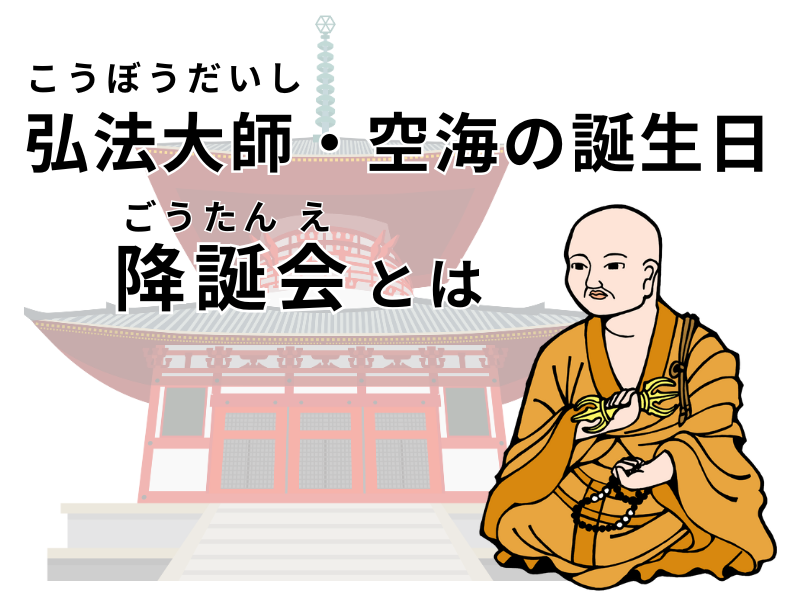
弘法大師(こうぼうだいし)・空海は、日本で真言宗を開き、真言密教を広めた人物です。この空海の誕生日にまつわる行事をご存じでしょうか?
仏教では、お釈迦さまの誕生日に合わせた「灌仏会(かんぶつえ)」、いわゆる「花まつり」がよく知られていますが、真言宗の寺院では、宗祖である空海の誕生日に合わせた「弘法大師降誕会(ごうたんえ)」という法要が、今も盛大に執り行われています。
今回は、弘法大師・空海の誕生にまつわるエピソードとともに、6月15日に行われる「弘法大師降誕会」についてご紹介します。
弘法大師・空海の降誕会とは?
6月15日は、“お大師さま”として親しまれる真言宗の開祖、弘法大師・空海の誕生日とされる日です。仏教では、宗祖や高僧の誕生日を祝う法要を「降誕会(ごうたんえ)」と呼びますが、この日には、全国の空海ゆかりの寺院で「弘法大師降誕会」あるいは「弘法大師誕生会(たんじょうえ)」という法要が行われます。
空海は平安時代初期の僧侶で、遣唐使として唐(中国)に渡り密教を学んだのち、日本で真言宗を開きました。仏教の布教だけでなく、書家、教育者、治水や土木の技術者としても多くの功績を残し、日本の歴史と文化の発展に深く関わった人物です。
弘法大師降誕会は、空海の誕生を祝い、その生涯と功績に思いを馳せながら、感謝を捧げる大切な法要です。和歌山県の高野山金剛峯寺(こんごうぶじ)や京都府の智積院(ちしゃくいん)をはじめ、いくつかの寺院では、「青葉まつり」として特別な行事が催されることもあります。
空海の誕生と子ども時代のエピソード
空海の子供時代については、あまりはっきりとした記録が残されていないようですが、多くの逸話が残されています。
神童と称された幼少期
空海は、774年(宝亀5年)6月15日、讃岐国多度郡(現在の香川県善通寺市)に生まれたとされ、幼名は眞魚(まお)と伝えられています。
母親が、自身の体にインドの高僧が入る夢を見て目覚めると、空海を授かっていたという逸話が残っており、空海は幼いころから聡明で信仰深く、「神童」と呼ばれていたそうです。
また、7歳のときには「仏の道で人々を救うことが自分の道ならば、お助けください」と誓願し、山から身を投げたところ、天人が現れ空海の体を抱きとめたという伝説もあります。 この場所は「捨身ヶ嶽」と呼ばれ、その麓にあるのが四国八十八か所霊場の第七十三番札所、出釈迦寺(しゅっしゃかじ)です。
学問と修行に明け暮れた少年期
15歳になると奈良の都に上京してさまざまな学問を学び、18歳の時に大学寮に入学。しかし、官僚を目指す出世の道に疑問を抱き、19歳を過ぎた頃からは、真に人々を救う道を求めて山林での修行に入ったとされています。この頃に空海が訪れた四国の山々は「四国八十八カ所霊場」を巡る「四国遍路」の原型になったと言われ、また、奈良の吉野山から和歌山の高野山までの山道は「弘法大師の道」と呼ばれ、巡礼道として復元されています。
空海は20歳〜30歳の頃に出家したとされており、その修行のさなか、土佐国(現在の高知県)の室戸岬で真言を唱えていると、明け方の空に輝く金星(明星)が口に飛び込み、その時に見えた景色が空と海だけであったことから「空海」と名乗った。との逸話も残されています。
なお、この時行っていた修行が、13歳になった子どもが寺社に参拝する「十三詣り」の由来になったとも言われています。
十三詣りについてはこちらで解説しています。
◆十三詣り(十三参り)はいつするの?お参りの時期や由来・意味・風習などを解説します
その後、さらに仏教への理解を深める中で、大日経という経典と出会い、その真理を求めて唐(中国)への留学を決意。遣唐使の留学僧として、唐の長安へ渡ったのでした。
空海が残した功績
真言宗を開き、密教の教えを広める
804年(延暦23年)、31歳で遣唐使の一員として唐の都・長安に渡った空海は、密教の高僧である恵果(けいか)のもとで本格的に学ぶこととなりましたが、わずか2年という短い期間で密教のすべての教えを授かり、その教えを日本に伝えました。
帰国後は、嵯峨天皇の許しを得て「真言宗」を開宗。和歌山の高野山を開くと、修禅道場として、山中に壮大な伽藍を建立し、また京都の東寺を教えの拠点として弟子の育成にも力を注ぐなど、実践を重んじる真言密教の礎を築いたのです。 空海が伝えた「即身成仏」の教え、すなわち、「修行や善行といった仏の生き方を実践することで、もともと誰もが持つ仏性に目覚め、生まれ変わることなく(この身のままで)仏の境地に至ることができる」という教えは、時代を超えて受け継がれ、今も多くの人々の心の拠り所となっています。
日本文化の発展にも貢献
空海は、仏教だけでなく、唐から様々な知識や技術を日本にもたらし、日本文化の発展にも大きく貢献しました。
「弘法筆を選ばず」とのことわざにも名前が残されていますが、空海は優れた書家としても知られており、日本書道史の中で特に優れた「三筆(さんぴつ)」の一人にも数えられるほどでした。また、教育者としても活躍し、学問に触れられるのは身分の高い人のみという時代に、身分や階級に関係なく学ぶことができる「綜藝種智院(しゅげいしゅちいん)」という学校を設立しました。更に、土木・治水の知識を生かし、日本最大級のため池と言われる香川県の満濃池(まんのういけ)の氾濫を防ぐ改修工事に尽力したこともよく知られています。 この他にも、空海に由来する逸話や伝承が各地に数多く残されており、人々を救うという志に生きた空海の姿を物語っています。
弘法大師降誕会では何をする?
弘法大師降誕会では、空海への感謝と敬意を込めて、寺院ごとにさまざまな法要や行事が行われます。
稚児大師像を安置した花御堂と呼ばれるお堂が用意され、経文に節をつけて唱える「声明(しょうみょう)」や法話、護摩祈祷、献花や献香などを行うのが一般的で、お釈迦さまの降誕会である「灌仏会」と同じように、稚児大師像に甘茶をかけるところもあります。また、寺院によっては「青葉まつり」と呼んで、舞や音楽の奉納、稚児などの行列が行われるなど、華やかな雰囲気に包まれます。 代表的なものをいくつか紹介します。
高野山(和歌山県)
高野山では、「青葉まつり」と呼ばれ地域を挙げた大きなお祭りになっており、幼少期の空海に見立てた「稚児大師」役の子どもを乗せた山車をはじめ僧侶や稚児などが練り歩く「花御堂渡御(はなみどうとぎょ)」は有名です。また、前夜祭には夜店がたち、明かりを灯した大きな「高野ねぶた」が巡行し町を彩ります。
東寺(京都府)
五重塔でも有名な東寺では、洛南高等学校の吹奏楽部による演奏と共に僧侶が入場し、法要では稚児大師像に甘茶が献じられます。また、「東寺流大師講 御詠歌(御詠歌)」の詠唱や、園児や児童たちが弘法大師・空海にご挨拶して歌を唄う、「おさなごのつどい」が行われるようです。
善通寺(香川県)
空海が生まれたとされる香川県の善通寺では、献香、献茶、百種のお供物で供養する「百味供養」のほか、「大師市」と呼ばれる市が立ち様々な催しが開かれます。また、この日に合わせ、国宝・金銅錫杖頭(こんどうしゃくじょうとう)の特別公開も行われています。
まとめ
弘法大師・空海の降誕会は、ただ誕生日を祝うだけでなく、その教えや功績に改めて思いを馳せる日でもあります。 空海はこの世を去った後、生前の行いをと尊んで貴人や僧侶に贈られる諡号(しごう)として、「弘法大師」を賜り、「お大師さま」と親しみを込めて呼ばれるようになりました。空海が生涯をかけて説いた教えと、その生き方は、今も多くの人々の心の拠り所として生き続けているのです。 もしお近くで法要や催しが行われていたら、足を運んでみてはいかがでしょうか。僧侶としてだけでなく、文芸・教育・美術・建築など多方面で功績を残した空海の面影にふれながら、今も受け継がれる信仰のあたたかさや、感謝の思いを感じる時間になるかもしれません。
空海が開いた真言宗や、その教えを説く「御詠歌」についても解説しています。また、仏教を開いたお釈迦さまの誕生日にまつわる記事もありますので、合わせてお読みください。








