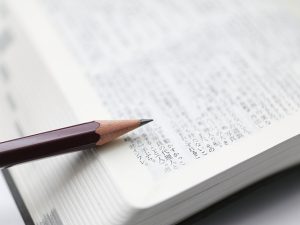お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
実は身近な仏教用語 /「隠元」とは?インゲン豆の由来となったお坊さんについて解説

ごま和えや炒め物によく使われるインゲン豆は、6月から9月ごろが旬です。インゲン豆は漢字では隠元豆と書きますが、名前の由来が隠元という仏教のお坊さんだということはご存知ですか。
このように日本語には、仏教にゆかりのある言葉が少なくありません。
隠元は中国出身の高僧で、インゲン豆のほかにも、さまざまな文化を日本にもたらしました。 今回は隠元の生涯や、彼が開祖となった黄檗宗(おうばくしゅう)について解説します。
隠元とはどんな人?
隠元は江戸時代の前半に活動した高僧(徳の高い僧侶)です。フルネームは隠元隆琦(いんげんりゅうき)。中国のお寺で住職を務めていましたが日本に招かれ、京都で黄檗宗を開きました。 隠元和尚や、隠元禅師(ぜんじ)と呼ぶこともありますが、禅師は禅に通じた優れた僧侶を呼ぶときに使う敬称です。
隠元の生涯
隠元は1592年、明(みん)朝時代の中国福建省で生まれました。出家して各地で修行を積み、福建省にある黄檗山萬福寺(おうばくざんまんぷくじ)の住職になります。遠い日本までその名声が届くほど、臨済宗の優れた僧侶として有名な存在でした。
その名声を聞きつけた長崎の僧侶たちが「日本に来てほしい」と何度も頼んだことで、1654年、隠元は63歳のときに弟子とともに日本に渡ります。
このとき、隠元は中国からインゲン豆を持ち込みました。ほかにも、スイカ、レンコン、タケノコなども持ってきていたと言われています。また煎茶による茶礼(されい)や、お寺の木魚などさまざまな文化も日本にもたらしました。
隠元や弟子たちによって伝えられたさまざまな文化は「黄檗(おうばく)文化」と呼ばれ、長崎から全国各地に広がり、今日の日本の文化にも影響を与えています。 隠元は現在の長崎県長崎市にある興福寺(こうふくじ)で1年ほど過ごしたあと、大阪の僧侶らの働きかけによって、現在の大阪府高槻市にある普門寺(ふもんじ)に移りました。
最初は日本にいるのは3年間という約束でしたが、のちに状況が変わり、隠元は徳川幕府4代目の将軍、徳川家綱とも面会しています。そして隠元に帰依(きえ)した(信じてよりどころとした)家綱や後水尾法皇の支援により、京都にお寺を開くことになります。
1661年、隠元は京都府宇治市に、中国で自らが住職を務めたお寺と同じ名前の萬福寺を開きました。この萬福寺には、隠元が自ら筆で書いた書が今も複数残されています。
隠元は中国に帰ることはなく、日本で僧侶として活動を続け、1673年に82歳で亡くなりました。
隠元の命日である4月3日には萬福寺で開山祥忌(かいさんしょうき)という法要を行い、隠元の好物だった油揚げをお供えしています。
また隠元にちなんで、4月3日はインゲン豆の日と制定されました。 さらに萬福寺がある京都府宇治市には、隠元にちなんで名付けられた隠元橋があるなど、感受性豊かで愛情深く多くの人を引き付けたという隠元は今も多くの人に親しまれています。
黄檗宗とは
隠元を開祖とする、日本の仏教の宗派の一つです。
隠元が開いた宇治市の萬福寺が大本山です。江戸時代のころは臨済宗の黄檗派という形になっていましたが、明治時代に入った1876年に黄檗宗として独立した宗派になりました。
今では臨済宗、曹洞宗とともに日本の三禅宗として知られています。
座禅やお茶を大事にする点は臨済宗や曹洞宗も同じですが、黄檗宗は中国式の仏教の影響が強い点が特徴です。
大本山である萬福寺は中国風の建築となっており、実際に訪れてみると中国に来たかのような雰囲気に驚くかもしれません。 儀式も中国の形式を受け継ぎ、お経も中国式の読み方で行います。そのためお経を聞いたときも、ほかの宗派と大きく異なる印象を受けるでしょう。
黄檗宗の茶礼とは
禅宗では、座禅と茶礼(されい)を大事にしています。茶礼とは、食事のあとや修行の合間などに1日数回、1つのやかんで淹れたお茶を僧侶皆で飲むことです。同じお茶を、ともに修行する仲間たちと一緒に飲み、皆の気持ちを一つにすることを目指します。
茶礼は、鎌倉時代に活躍した臨済宗の開祖、栄西(えいさい)が中国から日本に伝えたと言われています。当時は抹茶を使ったお茶を飲んでいました。
一方、隠元は中国から煎茶による茶礼を伝えました。黄檗宗の茶礼は現在も、煎茶を使って行います。
黄檗宗の普茶料理とは
茶礼は法要が終わったあとのもてなしとしても行われましたが、お茶に加えて料理でももてなそうと考え生まれたのが中国の精進料理に当たる普茶料理(ふちゃりょうり)です。
普という文字には普(あまねく)く、広く全体にという意味があり、普茶は「一般の人も含め、たくさんの人とともにお茶をする」という意味です。
長崎の郷土料理である卓袱(しっぽく)料理のもとになったのは、隠元によってもたらされたこの普茶料理だと言われています。
インゲン豆も、もともと普茶料理の材料として使われていました。
普茶料理では、1つのテーブルに4人が座り、大皿に盛られた中国風の料理を4人で平等に分けて食べます。上座や下座などの区別はなく、皆が穏やかな空気の中で食事することを大切にしています。
精進料理は味が薄そうというイメージがあるかもしれませんが、普茶料理は味がしっかりついていて食べやすい点も特徴です。
普茶料理は黄檗宗のお寺やさまざまな飲食店などで食べることができます。 黄檗宗における葬儀やお墓に関する特徴については、下記をご覧ください。
旬のインゲン豆をみんなで味わってみませんか
インゲン豆は、隠元の来日と共に日本に伝わりました。
お盆にみんなで集まり、お墓参りに行ったときには、故人との思い出を振り返って「昔おばあちゃんが作ってくれたごま和えはおいしかったね」「昔子供たちが食べられなかったインゲン豆、最近食べられるようになったんだよ」と話してかけてみてはいかがでしょうか。
このように日本語には普段の生活で使う言葉の中にも、仏教由来のものが多くあります。例えば「大丈夫」や「微妙」といった言葉も、もともとは仏教用語です。
日本語にも深く結びついた仏教は、日本の文化や行事にも深く根付いています。インゲン豆の旬でもある夏の「お盆」、お墓参りの時期である春と秋の「彼岸」の由来はご存知ですか。
下記の記事で詳しく解説しています。