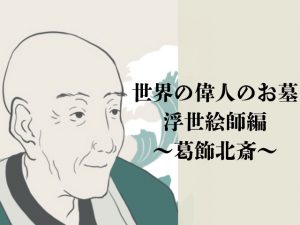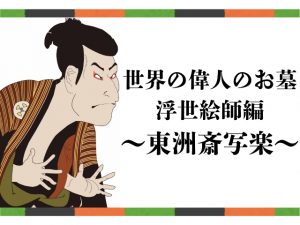お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
【おーい、応為】長澤まさみさんが演じる葛飾北斎の娘・葛飾応為お墓はどこにある?
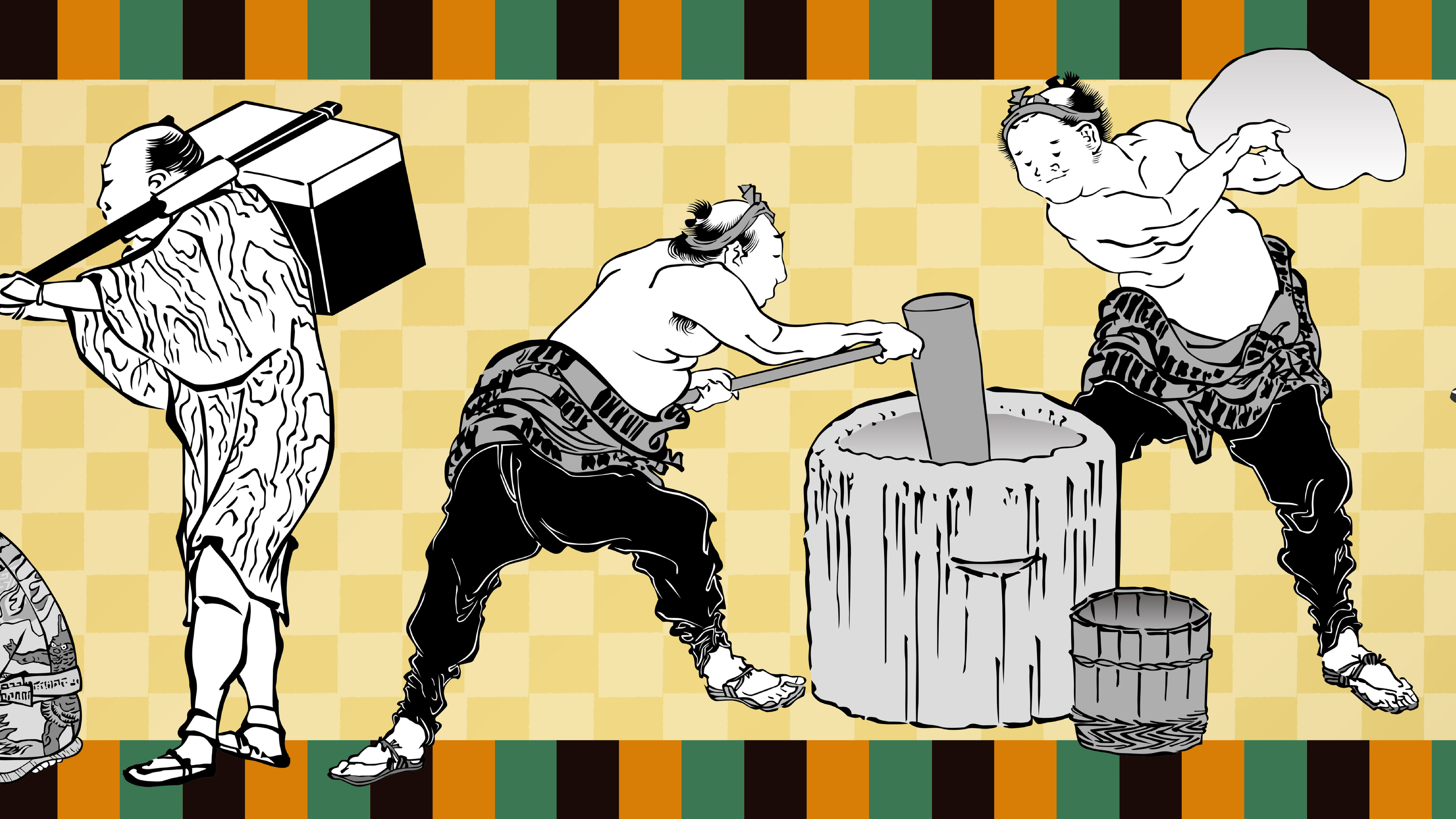
現在公開中の映画「おーい、応為」は、江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎(かつしかほくさい)の弟子にして娘、葛飾応為(かつしかおうい)を描いた映画です。
江戸の時代、絵を描くことはほとんど男性の領分とされていました。浮世絵の世界もその例に漏れず、名を残した絵師の多くは男性ばかりです。そんな中、葛飾応為は浮世絵の世界でその才能を開花させた女性として伝えられています。
単独で残した作品は多くはありませんが、斬新な感性と独特の光の表現で、浮世絵に新たな風を吹き込んだ存在として知られています。
今回は、そんな葛飾応為の生涯と作品、そしてそのお墓がどこにあるかについてご紹介します。
応為誕生
応為/本名:栄(えい)の詳しい経歴などは現在のところわかっておりません。北斎の生きた時代が江戸時代後期(1750年頃〜1867年)だったので、1800年頃の生まれではないかという説もありますが、定かではありません。北斎には5人(6人という説もあります)の子がいたと伝えられていますが、応為は北斎の三女として生まれます。
応為は「油屋庄兵衛(あぶらやしょうべえ)」の息子である「南沢吉之助(みなみざわよしのすけ)」に嫁いだと伝えられています。吉之助は町絵師「三代・堤等琳(つつみとうりん)」の弟子で、画業に励んでおり、「堤等明(つつみとうめい)」の名で作品を描いていました。しかし、絵の腕前に関しては妻となった応為の方が一枚上手で、夫の作品をからかうことがあったとも伝えられています。また、応為は家事なども全くしなかったため夫婦仲は次第に悪化し、ほどなくして離縁となったそうです。
実家に戻った応為は、北斎と「父と娘」として共に暮らしつつ、弟子として絵を学びます。
北斎の弟子として絵を学びます。ちなみに北斎から頻繁に「おーい」と呼ばれていたため、画号を「応為」としたと伝えられています(諸説あります)。
北斎の影響を受けた生活ぶり
応為の生き方や性格は父である北斎の影響を強く受けていたといわれています。気性は豪快で男勝りな一面があり、質素な暮らしを恥じることもなく、むしろ清貧を好んでいたそうです。食事は毎日のように煮売店 (現代でいう惣菜屋)で簡単に済ませ、家の中には食べ残しやごみが山のように積もっていたと伝えられています。しかし、父娘ともにそれを気にかける様子はなかったようで、炊事や掃除を女性が担うのが当たり前だった江戸時代において、応為の生活ぶりはかなり型破りであったと思われます。
とはいえ、応為は北斎ほど浮世絵以外の事に無頓着ではありませんでした。髪や衣服には気を配り、行儀も正しく父への思いやりを忘れなかったといわれています。ただし、掃除が苦手な点だけは父譲りで、部屋が汚れてくると新しい住まいを探して引っ越すのが常でした。
北斎の生涯での引っ越し回数は93回にも及んだといわれていますが、応為も晩年まで父と共に暮らしていたため、そのたびに引っ越しを繰り返したと考えられています。
そんな二人の暮らしぶりを伝える作品が、北斎の弟子・露木為一によって描かれた「北斎仮宅之図(ほくさいかりたくのず)」です。こたつに入り筆を取る北斎と、その傍らで父を見つめる応為の姿が描かれています。部屋の中には炭俵や食べ物の包装などが散乱し、生活の様子が生々しく表現されています。この原画は1923年の関東大震災で焼失してしまいましたが、当時の父娘の暮らしぶりを今に伝える貴重な資料とされています。
また、応為には晩年の奇妙な逸話も残っています。仏門に入ってからは、死を強く恐れ、踊念仏を欠かさなかったといわれています。さらに、地中の松の根に生える薬用キノコ「茯苓(ぶくりょう)」を常用し、不老不死の仙人になろうとしていたという話も伝えられています。加えて応為は、江戸時代に流行した豆人形とも呼ばれる小さな人形「芥子人形(けしにんぎょう)」を作って販売し、大きな財を得たともいわれており、その一風変わった生き方と発想力は、晩年になっても健在だったことがうかがえます。
応為の残した作品
卓越した画才を持っていた応為ですが、現存する作品はごくわずかしか確認されていません。その理由の一つは、応為の多くの時間が父・葛飾北斎の制作を支えることに費やされていたからです。特に、一般に出版された多色刷りの浮世絵「錦絵」においては、応為の名義で発表されたものは一枚も見つかっていません。自筆の署名(落款)がある肉筆画も現在確認されているのは十数点に過ぎません。
北斎の名で発表された作品の中には、実際には応為が手掛けた、あるいは補助として関わったと考えられるものも少なくないとされています。例えば1915年(大正4)年に刊行された雑誌『浮世絵』第7号には「春宵秘戯の画に北斎と称するものの多くは、北斎の娘・栄女(応為)の筆による」との記述が見られ、すでに当時から応為の代作説が語られていました。ただし、具体的にどの作品が応為によるものかを示す確かな証拠はなく、現在もその多くは推測の域を出ていません。
現存する応為の初期作として知られているのが、『狂歌国尽(きょうかくにづくし)』の一図「大海原に帆掛船図」です。刊行年は不明ですが、研究者の安田剛蔵による考証では、1810年(文化7)年以前に制作されたとみられています。この作品には「栄女筆」と署名されており、印章はありません。署名と時期から判断すると、応為が結婚する以前に描かれた唯一の作例と考えられています。
その後、応為は「葛飾応為」という画号を使う前に、「北斎娘辰女筆」という落款を用いた作品を残しています。この「辰女」は応為が用いていた別名であるとする説が有力で、その人物像についての詳しい記録は残っていません。しかし、その画風や人物描写の特徴は応為の作品と非常によく似ており、同一人物である可能性が高いとみられています。
研究者の間では、「辰女」は父の別号「北斎辰政」に由来するのではないか、あるいは応為が結婚後に用いた名前だったのではないかといった説が議論されています。ただし、「辰女」の署名が確認できる作品はわずか2点しかなく、署名のないものを含めても現存するのは3点にとどまっています。そのため、応為と辰女の関係、そして彼女の初期作品群については、今もなお多くの謎が残されています。
応為のお墓はどこにある?
葛飾応為のお墓ですが、実ははっきりとわかっていません。
晩年の葛飾応為は仏の教えに帰依し、信仰深い生活を送っていたと伝えられています。その最期については諸説あり、1855〜1856(安政2〜3)年頃に加賀前田家の庇護を受け、67歳の時に金沢の地で亡くなったとも、あるいは晩年に父・葛飾北斎が滞在した長野県小布施でその生涯を閉じたとも言われています。
いずれにせよ、その晩年の詳細は明確ではなく、応為の死の地や墓所も定かではなく未だ謎に包まれています。
ちなみに父・北斎の墓は東京都台東区元浅草にある誓教寺(せいきょうじ)の境内にあります。墓標には、北斎が晩年に自ら名乗った号「画狂老人卍(がきょうろうじんまんじ)」と刻まれています。これは、「絵に狂った老人」という意味で、生涯を絵に捧げた北斎らしい言葉です。さらに墓石には、北斎の辞世の句である「ひと魂で行く期(ご)ぞ見ゆる梅の花」が刻まれています。
【誓教寺(北斎のお墓)】 東京都台東区元浅草4-6-9】
また、応為が残した書状を見ることができる展覧会が2025年12月7日(日)まで開かれています。
【一般財団法人 北斎館】 長野県上高井郡小布施町大字小布施485】
まとめ
応為は、父・葛飾北斎とおよそ20年にわたり生活を共にし、北斎が亡くなる1849年(嘉永2)年まで、そばで支え続けました。北斎は数多くの弟子を持つ中で、最もその才能を認めていたのが娘・応為だったといわれています。実際に、北斎が「私の美人画は応為には及ばない」と語ったという逸話が残されており、父娘の間に深い信頼と尊敬があったことがうかがえます。
その卓越した画力を示す出来事として知られているのが、墨田区にある榛稲荷神社にまつわる話です。応為は神社に奉納するための奉灯(神前に供える灯火)の口絵を依頼されましたが、その絵があまりにも見事だったため、依頼主は奉納を惜しみ、自らの手元で大切に保管したと伝えられています。この逸話からも、応為の絵がいかに高く評価されていたかが分かります。
当時の社会では、絵師の世界は男性中心であり、女性が画業を営むことは極めて珍しい時代でした。 しかし、応為の技量は北斎をして舌を巻かせたと伝えられるほどだったことからすると、もし時代の壁がなければ、応為は父・北斎を超える活躍をしていたのかもしれません。
しかし、応為の作品には落款(署名)の残るものが少なく、記録も乏しいことから、その生涯の多くはいまだ謎に包まれています。それでも近年、応為はひとりの浮世絵師として再び注目を集め、その独自の美意識と画才が改めて評価されつつあります。
応為のお墓の所在は謎に包まれていますが、その父である北斎のお墓を訪れると、応為が生涯を通じて絵に込めた想いや、家族や師のためにどれほど努力し、どのような情熱で筆を握っていたのか。その熱い思いを少しでも感じ取ることができるかもしれません。
お墓は受け継がれる想いや絆があふれ、過去の偉人が遺したその功績までをも感じ取れる場所。そして、一緒に訪れた人との語らいの時間をもたらしてくれるのがお墓参りです。作品や教科書でしか知ることのない有名人・著名人ですが、実際にお墓を巡ることで、その人が生きていた時代を感じることができるのではないでしょうか。
マナーに十分に注意した上で、いろいろなお墓に参ってみてはいかがでしょう。
父である葛飾北斎や同じ浮世絵師である写楽、その他東京にある偉人のお墓に関する記事もございます。合わせてご覧ください。