お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
精進落としとは?食事内容・準備・当日の流れ・マナーを紹介
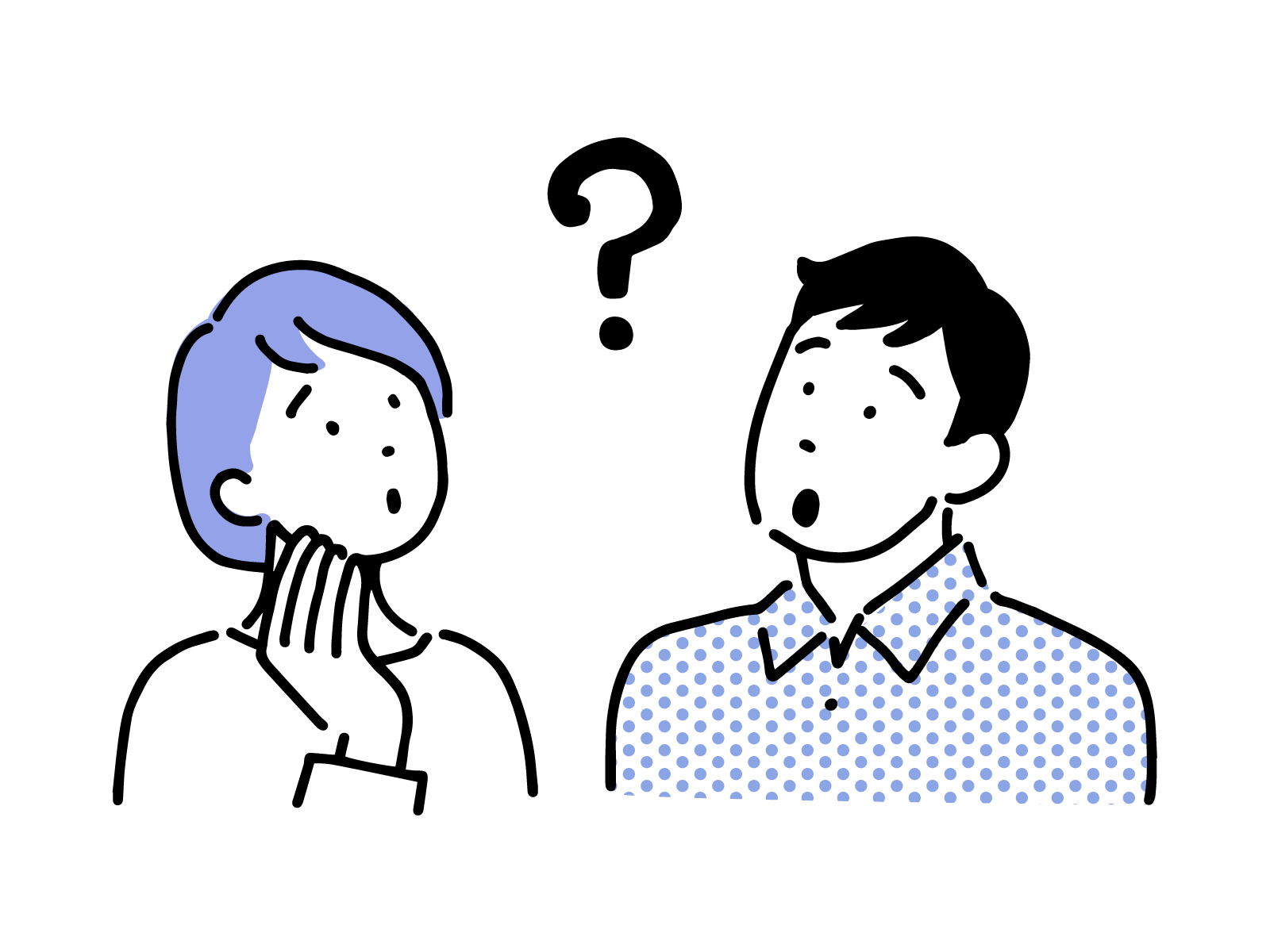
葬儀にまつわる会食の一つ、精進落とし。葬儀に参列し火葬後のお見送りまでされたことがある方なら精進落としの会食ときいて、「経験ある」「火葬場でたべるやつだよね?」「いや、お骨上げから戻ったあとだ」などなど色々経験談が出てくるかもしれません。
しかし、いざ自分が行う側の人になった場合「いつすればいいの?」「どういう準備が必要なの?」「そもそも何をどうすればいいのかわからない」など、よくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、精進落としの意味や食事内容、準備方法から当日の流れ、基本的なマナーなどについて詳しく紹介します。
精進落としとは?
精進落としとは、葬儀、告別式を終え、火葬場において故人の火葬を待つ間や火葬場から戻った後に故人を偲び、遺族や親しい人々が集まって食事を共にする会食です。かつては故人が浄土に旅立つまでの49日間、遺族は喪に服して精進料理(肉や魚を使わない料理)のみを食べていました。本来の「精進落とし」は49日目の忌明けにその制限を解き、一般的な、「精進」を落とす食事を共にするという意味で使われていました。しかし現代においては、故人を偲びつつ遺族が葬儀に参加してくれた親族や関係者に対して感謝の意を示し、その労をねぎらうために食事をふるまうという意味合いが強くなっています。
その為、かつては49日法要の後に行われていた精進落としの会食も前述のように葬儀後のタイミングで行われるようになりました。近年では親族も日本各地に離れて住んでいることが多く、親族や遺族の負担を軽減するという意味合いもあります。
一昔前までは火葬の時間が今よりもだいぶかかっていたこともあり、火葬を待つ間に精進落としの会食をとるということも多かったようですが、火葬場設備の最新化が進み火葬時間が短くなっている現代においては、火葬が終わって骨上げ後に別会場で行われることが多いようです。 また、どこで行うかによってお招きすべき範囲が変わり、予想される参列者の内訳によっては、食事にお招きすることでかえって気を使わせてしまうことになったりする場合や、終了時間が遅くなる場合には別日に改めて席を設ける場合もあります。
精進落としと通夜振る舞いの違い
精進落としと同じような意味合いで、よく混同されがちなのが「通夜振る舞い」です。通夜振る舞いとは、通夜の後に親族や参列者に対して提供される食事であり、意味合いとしては故人を共に偲びつつ、参加していただいた方々へ感謝を示すというものです。そのため精進落としと基本的には意味が同じで、違うのはその提供タイミングだけと思われがちですが、通夜振る舞いは大皿で提供され、摘まみやすい軽食スタイルが一般的で、精進落としは懐石料理などを個々の膳としてふるまうという風に食事の内容にも差があります。
なぜそういう差が出るのかといえば、通夜は事前に参列人数の把握が難しく、急な増減にも対応しやすくするということと、急なことであわただしい中、遺族、参列者共にゆっくりと時間をとっている余裕があまりないということがあげられます。逆に葬儀告別式後の精進落としは人数も事前に把握しやすく、逝去からあわただしくしていた遺族、親族にとっても一区切りとなり、故人を亡くした喪失感は消えないものの、少しゆっくりとできるタイミングになるため、といえるでしょう。
呼び名の違い
精進上げ、お斎(とき)、直来(なおらい)、精進落ち、忌中払い、精進明けなど精進落としには地域や宗派によって様々な別の呼ばれ方があります。関西では精進上げ。神道では直来。お斎は少し意味が違って通夜から葬儀、法要まですべての各仏事の後に設けられる会食を指しますが、別の呼ばれ方がこれほどあるということは、故人をしのんで関係者があつまり飲食を交わすという文化が昔から日本各地でとても大事にされてきたことの証明でもあると言えるでしょう。
精進落としの食事内容
現代において、精進落としの食事内容は、葬儀に参列してくださった方々に感謝の意を表し、労をねぎらうという側面が強いことから一般的には懐石料理や仕出し弁当など華やかな食事が供されます。
本来の意味からいえば内容としてはふさわしくない、生ものも提供されることが増えてきています。それほど内容にこだわる方も少なくなって、気を付けるべき点も減ってきましたが以下の点には注意しましょう。
- 偏りのない内容を心掛ける
参加者の年齢や趣味嗜好が偏っているのであれば、それに合わせればいいですが、一般的には老若男女幅広い層の参加者が想定されます。食事内容が偏らないようにすることはもちろん、飲み物も子供向けのソフトドリンクからビールや酒等のアルコール類も取り揃えておくのがよいでしょう。 - 鯛や伊勢海老を避ける
鯛や伊勢海老など縁起物と呼ばれる食材はお祝い事を連想させるため、精進落としには避けたほうが無難です。 - 僧侶への食事
宗派によっては口にすることができない食材があります。予め確認しておくなど配慮が必要な場合もあります。またもし参加を辞退されている場合はお膳料として食事代相場相当の5,000~10,000円をお渡しするのが一般的です。
逝去からばたばた続きで遺族としては一息つきたいところではありますが、できるだけ気を抜かず、故人の思い出話に花を咲かせながらも参列していただいた方々に感謝の気持ちをもって労いましょう。もし事前に調べられるのであれば参加予定の皆さんのアレルギー食材も確認したうえで、それを避けるようにすれば完璧です。
【3ステップ】精進落としの「準備」の流れ
何事にも当てはまりますが、事前の準備が重要です。以下の3つのステップに沿って、準備を整えましょう。
ステップ1:日程の決定
精進落としの日程は、葬儀の日程に合わせて決定します。火葬を待つ間に行うか、葬儀後か、それとも日程を変えてするのか検討しましょう。 葬儀とは別の日に行う場合、まず僧侶や参加してもらう方々の予定を確認しましょう。予定が合えばの前提にはなりますが、葬儀後の数日以内に行われることが一般的です。
ステップ2:場所の決定
日程を決めると同時に場所も確認します。仕出し弁当など、弁当の形で用意するのであれば、火葬場または斎場の待合室、あるいは自宅で。店内飲食の形であれば、場所を移してお店で。
もし場所を移してレストランや料亭で食事する場合は、参列者全員が座れるテーブルはあるのかの確認やお店までの交通手段を考慮しておくことが重要です。
ステップ3:出席者の決定
親族や親しい友人を中心に、出席者を決定します。僧侶の出席の有無、会社関係者までふくめるのかも検討しましょう。火葬を待つ間に行う場合やお骨上げ後に火葬場で行う場合には親族・友人・知人の別なく参加いただいた皆様に食事をふるまうのが一般的です。人数が増えそうだったり、分からない場合には多めに用意しておくか、大皿料理で対応しましょう。
【5ステップ】精進落としの「当日」の流れ
精進落としの当日は、以下の流れで進行します。
ステップ1:着席
参列者は、席順や座る位置に注意しながら着席します。親族のみで行う場合は遺族を除いた年長者を上座へ、親族以外も参加する場合は喪主や近親者が下座に座り、会社関係者や友人、知人が上座に着くことが一般的です。
ステップ2:喪主からの挨拶
食事が始まる前に、喪主または親族代表から挨拶を行います。挨拶では、参列者への感謝の気持ちや故人を偲ぶ言葉を述べます。大勢の前でしゃべるのに慣れていないと緊張するかもしれませんが参列してくれたことへの感謝の気持ちを、短い言葉でも問題ないのでしっかり伝えられればよいでしょう。
ステップ3:献杯
献杯は、故人を偲び敬意を表するために行われます。これは精進落としの場だけではなく法要の後の会食などでも行われることがあります。一般的には、まず喪主のあいさつの最後に、喪主の号令で全員で杯を手に持ちます。その後喪主が「献杯」と号令をかけ、静かに全員で唱和します。「乾杯」とはまったく異なるものなので杯をぶつけあったりするのはやめましょう。 献杯後に黙とうや合掌を行うこともあります。
ステップ4:食事の開始・歓談
献杯の後、喪主のすすめで食事が始まり、参列者同士で歓談が行われます。この際、静かな雰囲気で故人をしのびながら、その思い出を語り食事を楽しみます。
通常、喪主や遺族は御酌をして全員に感謝を述べて回ります。僧侶も参加いただける場合、喪主は僧侶に、他の参列者には遺族がまわるって挨拶というように役割分担をすることもあります。
ステップ5:終了の挨拶
終了時間が決まっていたり、開始から1-2時間経過し、いいころ合いになってきたらタイミングを見て開始の挨拶をした喪主または親族代表が終了の挨拶を行います。感謝の気持ちを込めて、参列者にお礼を述べ、精進落としが終わります。
葬儀関連を取り仕切る役目の喪主について詳しく知りたい方はこちらの記事も併せてお読みください。
精進落としの費用相場
精進落としの費用は、会場の場所や参列者の人数、料理内容によって大きく異なります。一般的には、1人あたり3,000円~10,000円程度が相場となっています。地域や関係性にもよりますが基本的には飲料を含まない金額で5000円程度の食事を用意するのが無難です。
あくまで相場なので、豪華な料理を提供する場合や酒豪の方が多い場合、費用は当然高くなります。
精進落としの基本マナー
精進落としの席では、一般の食事会以上に席順に気を付けるのが重要です。その他にも一般の食事会同様気を付けるべき基本的なマナーもありますので紹介していきます。
- 席順のマナー
喪主や近親者が参加者に感謝を表す会食になります。もてなす側の喪主や近親者は下座につきましょう。僧侶が参加いただける場合、最上座は必ず僧侶に座っていただきましょう。親族以外も参加する場合は、会社関係者や友人、知人に上座についてもらいましょう。 - 食事のマナー
祝い事の席ではなく、あくまで故人を偲ぶ場なので暴飲暴食やはしゃぎすぎ、よっぱらいすぎたりするのは控えましょう。 - 時間のマナー
故人との思い出を語り合い、お酒も入ることでついつい長くなってしまうこともあるかもしれません。どうしても話したりないことがあるのであればそれはまた後日に。参加者も遺族も疲れがあるでしょうから引っ張りすぎると後日にまで疲れを残してしまうことに。1-2時間程度で切り上げるのが無難です。
精進落としは、遺族から僧侶と参列者へ向けて感謝の意を表す重要な場です。精進落としを行わないことは一般的にマナー違反となりえます。しかし近年各々の事情から精進落としを行わず、返礼品の形などで謝意を表すことも選択肢の一つとして増えていることも事実です。ただし、その選択をする場合はマナー違反ととられないよう必ず事前にお知らせすることが大切です。
万が一のための準備はあらかじめ
身の回りでご不幸があった時はもちろん、何事についても、いざというときに慌てずに行動するために手順を確認して準備できるものはあらかじめ準備しておくことが重要です。
万が一の時に目の前のことを一つ一つこなしていくことに忙殺されて一番大事な故人との別れの時間がせわしないものになってしまうと悔いが残る結果になってしまうかもしれません。葬儀社の事前確認はもちろん、墓石や墓地・霊園は生前から用意できる場所もあります。生前にお墓を用意するのは、相続税対策になるなどのメリットがあるためおすすめです。
下記の記事でメリットについて解説しているため、あわせてお読みください。
◆お墓が相続税対策(節税)になるってホント?税金について解説。
逝去してから納骨までの全体の流れを把握しておきたい方や「忌明け」や「喪中」などの語句の意味を詳しく知っておきたい方にはこちらのコラムもおすすめです。あわせてお読みください。








