お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
お月見はいつやるの?〜十五夜・十三夜の起源や風習に込められた意味を解説〜
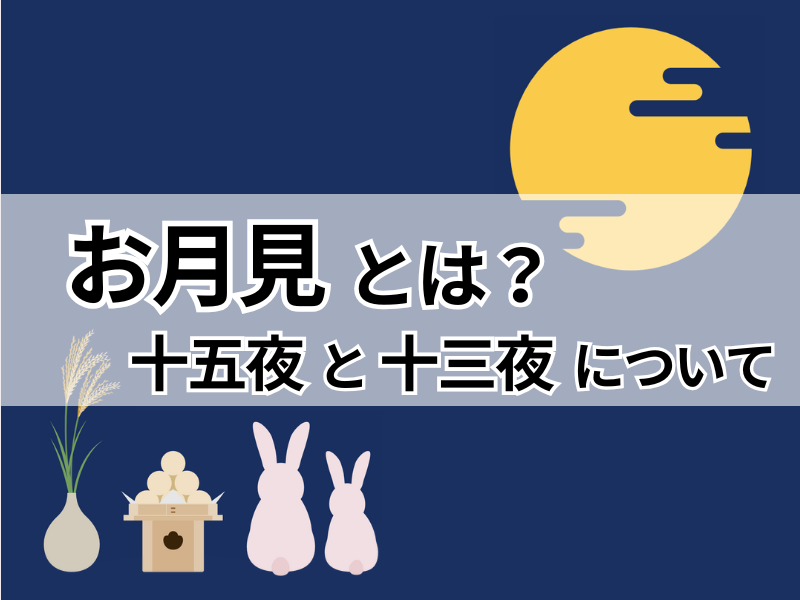
秋の風物詩にもなっている「お月見」。お団子やススキを飾ったり、秋の味覚をいただいたりして楽しむほか、地域によっては古くからの習わしも残る、日本の伝統行事です。全国的に広く知られているお月見ですが、その一方で、「十五夜って毎年違う日なの?」「十五夜は知っているけど十三夜って?」という方がいらっしゃるかもしれません。
今回は、秋のお月見の行事である「十五夜」と「十三夜」について、その起源や具体的な日にち、風習に込められた意味などを詳しく解説していきます。
お月見とは?
お月見は、秋の澄んだ夜空に浮かぶ月を眺めながら、収穫に感謝し豊作を祈る、日本の伝統行事です。一般的には、「十五夜(じゅうごや)」がよく知られていますが、その一ヶ月ほど後に訪れる「十三夜(じゅうさんや)」にも、お月見をする習わしがあります。
お月見には、お団子やススキ、収穫した作物をお供えするのが一般的で、特に満月に近い月が見られる「十五夜」は、「中秋(ちゅうしゅう)の名月」とも呼ばれ、各家庭だけでなく、施設や各地で催しが開かれるなど広く親しまれています。
十五夜と十三夜はいつ?
「中秋の名月」を楽しむ「十五夜」
「十五夜」とは、旧暦の8月15日の夜を指します。
旧暦では新月を1日(ついたち)と数え、15日は満月、またはそれに近い月が見える日。また、7・8・9月を秋としたことから、旧暦8月15日は秋のちょうど真ん中にあたり、空気も澄んで月がひときわ美しく輝きます。そのため、この日の月は「中秋の名月」と呼ばれ、昔から特別に愛でられてきました。芋類の収穫時期にもあたり、お供えに用いられたことから、「芋名月」とも呼ばれています。
「十五夜」という言葉は、もともと毎月15日の夜を意味しましたが、とりわけ美しい月が見られる旧暦8月15日を指す言葉として定着し、今に伝わっています。
現在の暦(新暦)では9月中旬〜10月初旬頃にあたり、2025年は10月6日、2026年は9月25日、2027年は9月15日となります。
「後の名月」と呼ばれる「十三夜」
十五夜からおよそ一ヶ月後、旧暦の9月13日の夜を「十三夜」と言います。新月から13日目にあたり、満月に少し満たない控えめな月が、完璧ではないものに美しさを見出す日本人らしい感性から「十五夜に次いで美しい」とされ、古くからお月見の行事が行われてきました。
台風などの影響で天候が不安定になりがちな十五夜と比べ、十三夜は晴天に恵まれることが多いことから「十三夜に曇りなし」と言われ、お月見に最も相応しい時期とも考えられていたようです。
現在の暦(新暦)では10月中旬〜11月初旬頃にあたり、2025年は11月2日、2026年は10月23日、2027年は10月12日、となっています。
十三夜の月は、中秋の名月の後に愛でるという意味で「後(のち)の名月」と呼ばれるほか、秋の最後の月であることから「名残の月」、栗や豆が実る時期であることから「栗名月」「豆名月」とも呼ばれてきました。また、十五夜か十三夜の片方だけを楽しむ「片見月(かたみづき)」は縁起が良くないとされ、両方を楽しむ「二夜(ふたよ)の月」という風習も生まれました。
お月見の行事の起源と歴史
中国の伝統行事「中秋節」と十五夜
日本におけるお月見の起源は、中国に古代から受け継がれている伝統行事「中秋節」にあるとされています。
中秋節は、秋の真ん中にあたる日に、欠けたところがない満月にちなんで家族団欒を楽しみ家族の健康や幸福を祈る行事です。現在でも、祝日の一つとして大切されており、月餅などの丸いお菓子を分け合って食べる風習などがよく知られています。
この中秋節の行事が、仏教や季節行事とともに日本へ伝わり、平安時代には貴族の間で「十五夜」月を鑑賞する「観月の宴」として楽しまれるようになりました。月を眺めながらお酒を酌み交わしたり、船の上で詩歌や管弦を楽しんだりする風流な行事として親しまれ、夜空に浮かぶ月だけでなく、川面やお酒が入った盃に映る月を愛でたとも伝えられています。
日本で生まれた十三夜
貴族の間で「観月の宴」が流行した平安時代、日本独自のお月見として生まれたとされるのが「十三夜」です。
その始まりは諸説あり、919年(延喜19年)9月13日に後醍醐天皇が清涼殿で催した月見の宴や、1135年(保延元年)9月13日に開かれた月見の宴で、宇多天皇が「今夜の名月は並ぶものがないほど優れている」と賞したことなどに由来すると考えられています。
満月に欠ける月を愛でるようになった理由は明らかではありませんが、今も茶道や華道などに受け継がれ、「侘び寂び(わびさび)」とも言われる、自然の中にある不完全さや儚さに美を見出す日本人独特の精神に通じるところがあるのかもしれません。
侘び寂びやもてなしの精神が受け継がれる茶道については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
庶民へ広がったお月見
月の満ち欠けは、農耕文化とも深い結びつきがあり、神話に「月読命(つくよみのみこと)」という月の神様が登場するなど、日本でも古くから月の存在が大切にされてきました。
そのため、江戸時代に入り、お月見の行事が庶民にも広がると、月を鑑賞するだけでなく、神様やご先祖様に秋の収穫の感謝を伝え五穀豊穣を祈るという意味合いが込められるようになりました。こうして、月にお供え物をする、現在に受け継がれる「お月見」の行事が形作られていったと考えられています。
お月見にまつわる言い伝え
秋のお月見の行事には、月にまつわる古い言い伝えも残されていますのでご紹介します。
月に昇った仙女の伝説
中国の神話の中には、中秋節の始まりとも伝わる『嫦娥奔月』(じょうがほんげつ/嫦娥、月に奔(はし)る)という伝説が残されています。
「遠い昔、后羿(こうげい)という英雄が、女神である西王母から不老不死の霊薬を賜りました。しかし、妻の嫦娥(じょうが)がこの薬を飲んで逃げてしまい、月の宮で一人寂しく暮らすことになりました。」
妻の嫦娥が薬を飲んだ経緯は、悪い弟子から薬を守るため、神の力が欲しくて薬を盗み飲んだためなど、諸説ありますが、のちに、后羿が嫦娥を想いお供え物をして月を偲んだことから、中秋に月を祀る行事が広まったとも言われています。
月のうさぎ
日本では、満月の中に影のように映る模様がうさぎのように見えることから、「月にはうさぎが住み、餅つきをしている」と言われることがあります。その由来とされているのが、お釈迦様の前世に関する出来事をまとめたとされるインドの説話集『ジャータカ』に書かれた物語です。
「昔、猿と狐と兎の3匹が、空腹で倒れている老人を見つけ、その老人のために食べ物を探そうと考えましたが、兎はどんなに苦労しても何も持ってくることができず、自らが火に飛び込み、自分の身を老人に捧げました。実はその老人の正体は帝釈天(たいしゃくてん)という神様で、その慈悲深い行為に感動した帝釈天は、兎の行いを後世にまで伝えるために、兎の姿を月の中に映したということです。」
この物語が、中国を経て日本へと伝わる過程で変化し、「うさぎが餅をついている」と言われるようになったようです。(中国では、前述で紹介した月の仙女・嫦娥が月に行く際に抱いていたうさぎが、不老不死の霊薬をついているとも言われています。)
餅をついていると言われる理由は諸説あり、うさぎが帝釈天にお供えするためとも、人々が食べ物に困らないようにとも伝えられています。満月を意味する「望月(もちづき)」が由来とする説もあるようです。
お釈迦様については、その生涯についても解説する記事がございます。
◆仏教の開祖 お釈迦様の生涯とは?8つのキーワードで簡単に解説
お月見のお供えや風習
月見団子
お月見の代表的なお供えと言えば、月見団子です。満月に見立てた丸い団子を、十五夜には15個、十三夜には13個、ピラミット型に積み上げて供えるのが一般的で、豊作への感謝や豊穣、幸福、健康といった願いを月へ届ける意味合いがあるとされています。ただ、団子の数を一年間の満月の回数に合わせた12個(うるう年には13個)や、15を簡略化した5個にする、団子の形を、里芋をかたどった細長い形や、丸い団子の真ん中を凹ませた形にするなど、地域によって異なる慣わしもあります。
ススキ
ススキもお月見のお供えの定番で、月の神様をお迎えし、無事に豊作になるようにとの祈りをこめて飾られます。
ススキは、茎が空洞になっていることから、神様の依り代(よりしろ)として、また、その切り口が鋭いことから、作物や家を災いから守る魔除けとして、用いられてきました。実りの象徴で神様が宿るとされる稲穂の代わりに用いられたとも言われています。
里芋、豆、栗など、収穫した作物
お月見のお供え物は、もともと、収穫した作物が中心だったと言われており、芋名月、豆名月、栗名月との呼び名にもある通り、十五夜には芋類、十三夜には豆や栗をお供えする風習があります。
また、かぼちゃ・きのこ、柿、梨、葡萄など、季節の野菜や果物をお供えすることもあり、特に葡萄のようにツルのある植物は、お月様や人とのつながりが強くなると言われています。
月見酒
お月見をしながらお酒を楽しむ「月見酒」も、古くから日本に残る趣ある風習です。古来日本では、秋の収穫を神様に感謝し、月を眺めてお酒を飲む「月祀り(つきまつり)」という風習があったと言われています。これが、平安時代に宮中で始まった「観月の宴」とも結びつき、神々に感謝を捧げてお酒をいただく風習が定着していったと考えられています。
お供えしたものをいただく
お月見のお供えは、食べて楽しむことも大切な行いとされています。これは、神仏へのお供え物のお下がりをいただく(食べる)ことで、食べ物の命や神仏とのつながりを感じ、その力を分けてもらうという、お月見に限らず、日本で古くから受け継がれている習わしです。
地域に残る風習
十五夜には、一部の地域に伝わる風習もあります。
中でもよく知られているのが「お月見泥棒」「団子盗み」などと呼ばれる、十五夜に、子供たちが各家々を回って、お供え物を盗む(もらう)という風習です。子どもは月のお使いとされ、お供え物を盗まれると豊作になると言われていたようです。現在では、「お月見ください」「お月見泥棒です」「十五夜ください」などと声をかけて、お菓子やお団子をもらうといった形で受け継がれています。
そのほか、鹿児島や沖縄には、踊りや綱引き、相撲などで豊作や健康を祈願する行事が受け継がれています。
お月見に合わせて、お墓参りはいかがでしょうか
日本では昔から、ご先祖様が土地や家の守り神となり、田畑の豊穣や家族の繁栄をもたらすと信じられてきました。
十五夜や十三夜は、美しい月を楽しむだけではなく、秋の実りに感謝し、幸福、健康といった願いを月へ届ける行事でもあります。そんなお月見の日には、月だけに感謝や願いを届けるのではなく、日々見守ってくれているご先祖様への感謝を込めてお墓参りをするのもおすすめです。
墓前や仏壇に月見団子をお供えして、「今夜は一緒に満月を楽しみましょう」と語りかけるのもよいでしょう。
こうしてご先祖様の存在を身近に感じながら迎えるお月見の夜は、家族の絆を深める、あたたかなひとときとなるはずです。
まとめ
季節の移り変わりを繊細に感じ、自然と共に暮らしや文化を育んできた日本人にとって、月は暦や農耕の目印であると同時に、夜空に高く昇り美しく輝く神聖な存在でもありました。その月への感謝や祈りの心が形となり、お月見の行事として今に受け継がれています。
現代のせわしない日々の中では、ゆっくりと月を眺めることも少なくなったかもしれません。だからこそ、お月見は、日本人が大切にしてきた「季節を感じ、自然や万物に感謝する心」に触れるひとときとなるでしょう。
今年の十五夜、十三夜は、行事の由来や言い伝えなどに思いを馳せつつ、家族でお月見を楽しんでみてはいかがでしょうか。
秋のお墓参りにおすすめの花や、この季節に咲く彼岸花についての記事もありますので、併せてご覧ください。







