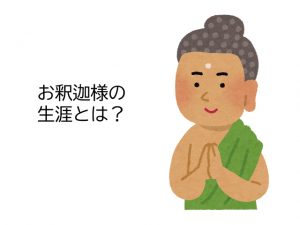お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
座禅のやり方は?自宅でもできる初心者向けの方法を解説

今、座禅が静かなブームになっていて、各地のお寺でも座禅の体験会が開かれています。
座禅は姿勢がよくなる、リラックスすることで心に余裕ができるなどの効果があるため、気になっている人も多いのではないでしょうか。
座禅は特別な道具を用意しなくても、自宅などで気軽に始めることが可能です。
そこで今回は、自宅でもできる初心者向けの座禅方法について解説します。
そもそも座禅とは?
座禅は、姿勢を正し座った状態で行う仏教の修行の1つです。精神を統一し、雑念などを払った無我の状態になることを目指します。
仏教の開祖であるお釈迦様が、菩提樹の下で7日間座禅を行ったあとに悟りを開いたことにちなんで行われるようになりました。特に曹洞宗、臨済宗、黄檗宗などの禅宗と呼ばれる宗派で重視され、座禅教室もこれらの宗派のお寺でよく開催されています。
禅は、サンスクリット語のディヤーナを語源とする禅那(ぜんな)を略した言葉です。ディヤーナには、心が落ち着いている状態という意味があります。なお座禅は正式には「坐禅(ざぜん)」と表記しますが、「坐」が常用漢字外のため、一般的には「座禅」と書かれることが多いようです。
禅は、今流行しているヨガとも関わりがあります。ヨガと座禅の関係については、以下の記事をご覧ください。
座禅と瞑想の違い
座禅と瞑想はどちらも心を落ち着ける効果がありますが、実は目的ややり方に違いがあります。
座禅はこのあと説明するように、座り方や手の組み方など細かい決まりがあります。また目は閉じず、開いたまま視線を下に落とした状態にする点も特徴です。目的は心を無にして、何も考えない状態になることです。宗派によっては、座禅は目的を持たずにただ座り続けることが大事というという考え方も存在します。
一方、瞑想は座り方などのやり方に詳しい決まりはありません。目を閉じて行うことが多いものの、落ち着いて気持ちを集中できれば、自分の自由な体勢で大丈夫です。集中力を高めるなど具体的な目的を持って行われることが多いようです。
座禅に必要な準備
大がかりな準備は必要ありませんが、下記のような点を意識することでスムーズに座禅を始められます。
用意する道具
床や畳に座って行う場合は、お尻の下に敷くクッションがあるとよいでしょう。座布団を半分に折って代用することも可能です。イスに座って行っても問題ありません。
曹洞宗のお寺では、厚くて丸いタイプの坐布(ざふ)とよばれる座禅用の座布団を使用します。このタイプの坐布を使うメリットは、膝や腰の負担が軽減される点です。
臨済宗でも坐布を使いますが、こちらは大きな長方形の座布団に、小さな半座布団を重ねるタイプです。座禅中に足が床に触れることを防げるほか、足の痛みを緩和できる効果もあります。
座禅を本格的に行うなら、こうした専用の座布団を用意するのもおすすめです。
服装
服装は体を締め付けない、ゆったりしたものを選びましょう。足を組みやすいよう、ゆとりのあるデザインのズボンがおすすめです。アクセサリーや時計は外しておきます。
場所
周囲の音が気にならない、静かな場所で座禅を行いましょう。座禅をしている間、周りのものが目に入って気が散らないように、部屋を片付けておくことも大切です。
準備体操
肩や腕などを動かし体をほぐしておくことで、座禅の姿勢を取りやすくなります。
座禅のやり方
宗派やお寺によって細かいやり方には違いがありますが、主な流れは下記の通りです。
- 座布団などを置いて座禅する場所を整える
- 立った状態で座禅する場所に向かって合掌、一礼する
- 座布団がお尻の下に来るように座る
- 足を組む
初心者は組みやすい半跏趺坐(はんかふざ)がおすすめです。
曹洞宗のやり方では、あぐらをかいた状態から、左足を右太ももの上に上げ、右足は左太ももの下に隠すように入れ込みます。臨済宗では右足を左太ももの上にあげ、左足を右太ももの下に入れ込みます。慣れてきたら本格的な結跏趺坐(けっかふざ)にも挑戦してみてください。結跏趺坐がお釈迦様が悟りを開いたときの組み方だと言われています。こちらも曹洞宗では左足を右太ももの上に置き、次に右足を左足の下から左太ももの上に乗せ、両方の足の裏が見える状態にします。臨済宗では右足から同じ手順で組みます。
イスに座って行う場合、足は組まずに浅く腰掛け、背もたれによりかからず背筋をまっすぐに伸ばしましょう。 - 手を組む
法界定印(ほっかいじょういん)と呼ばれる形を作ります。右の手のひらを上に向けた状態で組んだ足の上に乗せ、同じように手のひらを上に向けた左手を重ねます。そして左右の親指が少し触れるくらいに近づけ、手で楕円形を作ってください。
初めて行うときは結手(けっしゅ)もおすすめです。まず左手の親指を右手で握り、左手の親指以外の指で右手の甲を包み込むようにして組みます。 - あごを引き、背筋をまっすぐに伸ばす
- 目の位置を調整する
自然に開いた状態で視線を下にします。1mくらい先の床を見るイメージで視線を下げると、半眼(はんがん)という仏像の目のような状態になります。 - 腹式呼吸を意識して、何度か深呼吸する
- 前後左右に体を揺らす
左右揺振(さゆうようしん)と呼ばれる動きです。組んだ手をいったんほどき、手のひらを上にした状態で右手を右太もも、左手を左太ももに置き、体を前後左右に揺らします。最初は体を大きく揺らし、だんだんと小さく揺らす形に変えながら、体の中心になる位置を見つけて止まりましょう。そして、もう一度手を組みます。 - 自然に呼吸をしながら座禅を行う
座禅をしている間は何もかも考えない状態になれるのがベストですが、実際にやってみると何かを考えてしまうことも多いはずです。そんなときは無理に考えを消そうとせず、何かを考えたまま過ごしても大丈夫です。
呼吸の回数を数える数息観(すそくかん)も試してみましょう。息を吐き出すときに1、2、3…と数を数えていきます。10まで数えたら、また1に戻って数え直してください。
お坊さんの修行では45分を目安に座禅を行いますが、自宅で行う場合はもっと短くても問題ありません。慣れない間は5分から15分くらいがおすすめです。 - 座禅の時間が終わったら、その場で合掌、一礼し組んだ手のひらを解く
- 左右揺振を行う
始めるときとは逆に、最初は小さく、だんだんと動きを大きくしていきます。 - 組んだ足を解く
- 立ち上がったら座布団の形を整える
- 自分が座禅していた場所に向かって合掌、一礼して終わる
お寺の座禅では叩かれるの?
座禅と聞くと、警策(曹洞宗では「きょうさく」、臨済宗では「けいさく」)と呼ばれる長い棒を持ったお坊さんにバシッと叩かれるイメージを持つ人もいるかもしれません。
しかし実際には、自分から希望しなければ、警策で叩かれることはありません。
警策は罰として相手を叩くためではなく、修行にいそしむ自分を励ましてほしいと望む相手に、励ましの気持ちを伝えるために使われているのです。
しかし実は、警策は江戸時代から始まったと言われており、仏教の長い歴史から見ると比較的新しい習慣です。また、そもそも相手を叩く行為がお釈迦様の教えに反するという考え方も存在しており、現在では警策で叩く行為をやめるお寺も出てきています。
座禅を通して自分に向き合ってみては
座禅は足の組み方などの作法が細かく決められているため、最初は難しいと感じるかもしれません。しかし最初は5分だけやってみるなど、少しずつでも日常に取り入れることで、日常のストレスから離れ心が落ち着く状態を感じられるようになるでしょう。
座禅と同じように自分に向き合う方法として、お墓参りに行くのもおすすめです。
お墓はご先祖様とのつながりを感じながら、自分自身についてゆっくり考えるきっかけを作れる場所です。お墓でご先祖様に語りかけながら自分の気持ちを整理してみることで、今まで気づかなかった解決の道が見つかるかもしれません。