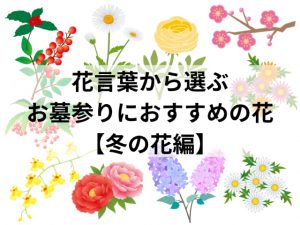お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
年末の大掃除と「煤払い(すすはらい)」〜起源や由来、込められた意味を解説します〜
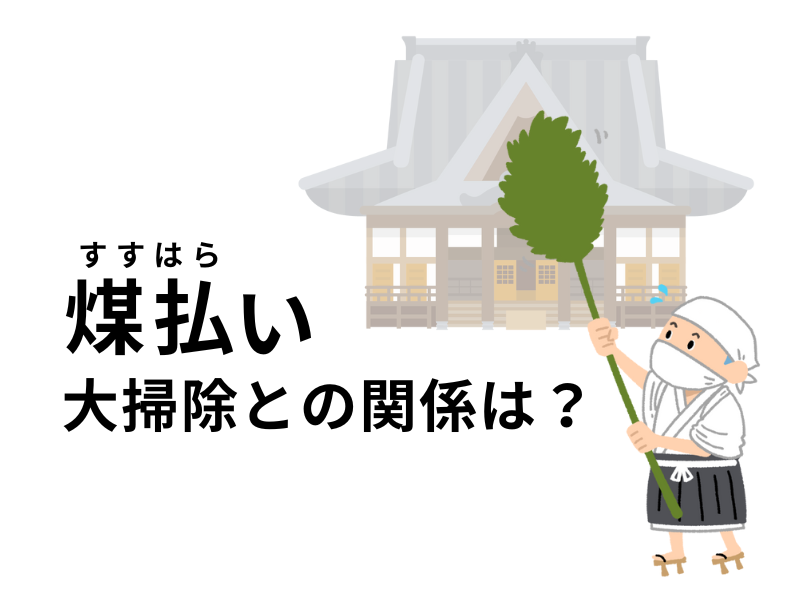
年末に向けて何かと慌ただしくなる12月ですが、月の半ばごろにもなると、年末の大掃除に取り掛かる家庭が増えてきます。
ちょうど同じ頃に全国の神社やお寺で行われるのが、「煤払い(すすはらい)」の行事です。新聞やテレビで取り上げられることも多く、年の瀬を告げる風物詩となっていますが、この煤払いが、実は年末の大掃除の起源にもなっていることはご存知でしょうか?
今回は、煤払いの始まりや、行事に込められた意味を解説し、現在の大掃除との繋がりや、今に伝わる風習についてもご紹介していきます。行事の意味や大掃除との関係を知ることで、大掃除のイメージがこれまでと違ったものになるかもしれません。
煤払い(すすはらい)の意味や由来
煤払いとは
「煤払い」とは、お正月を迎えるにあたり、年末に家の内外を大掃除し1年の汚れを払い清める、古くから続く日本の年中行事です。
全国の神社仏閣において、毎年12月13日を中心として12月中旬頃に行われるのが一般的で、畳や天井、仏像などの埃を払う年末の代表的な行事となっているほか、多くの家庭や会社における「年末の大掃除」として受け継がれています。
なお、煤(すす)というのは火を燃やした後に出る黒い燃えカスのことです。竈(かまど)や囲炉裏(いろり)、行灯(あんどん)などを使っていた時代には、家中に溜まる煤汚れを払い掃除をしていたことから「煤払い」と呼ばれています。
どんな意味のある行事なの?
12月13日は、正月を迎えるための準備を始める日として、「正月事始め(ことはじめ)」とも呼ばれています。この日から半月ほどかけて行われる、正月準備の最初に行われてきたのが「煤払い」です。
日本では古くから、ご先祖様の霊が山や田畑に宿り、正月には「年神様(歳神様)」となって家々に福徳を授けると信じられてきました。お正月は、この年神様を家にお迎えする行事であり、煤払いには、「年神様をお迎えするために、煤や埃一緒に1年分の穢れや厄を祓い、家を清める」という儀式的な意味合いも込められています。
12月13日となった理由
煤払いをする日の由来については諸説ありますが、旧暦12月13日が「鬼宿日(きしゅくにち)」という、鬼が宿にこもり出てこないため何事をするにも良い吉日にあたることから、この日に正月準備を始める習わしが定着していき、明治時代に新暦に切り替わってからも、その伝統が受け継がれてきたと考えられています。
また、この日は「松迎え」とも呼ばれ、かつては門松に使う松やお雑煮を炊くための薪などを山へ取りにいく習慣があったようです。さらに、正月準備を始めるだけでなく、「物忌み(ものいみ)」といって、正月にむけて飲食や行動を慎んで心身を清める期間の始まりとも言われていました。
正月準備を始める日というと、関東を中心に12月8日を「事始め」、2月8日を「事納め」としてお正月の祭事を行う習わしもあるように、一部の地域では12月8日に煤払いを含めた正月準備を始めるところもあります。
煤払いの起源と歴史
始まりは平安時代の大切な儀式
煤払いの起源は、平安時代の宮中行事にまで遡ります。平安時代の法律についてまとめられた書物である『延喜式(えんぎしき)』には、「煤掃き」としてその方法までが詳しく書かれ、新年の年神様を迎えるために厄払いをする大切な儀式として行われていたようです。
神社仏閣を清める行事に
仏教が広がりを見せた鎌倉時代から室町時代ごろには、寺院や神社を清める行事として定着したと言われています。仏教では、「掃除が心の汚れを取り除く」というお釈迦様の教えが伝えられており、こうした考え方も、煤払いの行事が広まる土台となったのかもしれません。
毎年12月20日に行われる、全国的にも有名な京都の東本願寺、西本願寺の煤払いは、平安時代頃にはすでに行われていたとされる歴史ある行事です。東西でやり方に違いはありますが、それぞれに僧侶や門信徒など300人余りが集まり、広い堂内に並んで、両手に持った竹の棒で畳を叩きながら進んだり、舞い上がった埃を2mほどもある大きな団扇であおぎ出したりして大掃除をする様子は圧巻です。そのほか、各地の多くの寺社仏閣でも煤払いの行事が受け継がれており、年末の訪れを感じさせる、この時期の風物詩となっています。
一般庶民に広まった江戸時代
江戸時代になると、前述した鬼宿日にあたる12月13日を「煤納めの日」と定めて江戸城の大掃除が行われるようになりました。これがきっかけとなり、一般庶民にまで煤払いの文化が広がったと伝えられています。煤払いは、季節の節目の儀式として、「煤取り節句」「十三日節句」などとも呼ばれていたようです。また当時は、煤払いが終わると胴上げをしたり、ご祝儀のお酒が振る舞われたり、家族でご馳走を楽しんだりと、賑やかにおこなう年中行事でも合ったようです。
煤払いの習わし
笹竹で汚れを払う道具「煤梵天(すすぼんでん)」
伝統的な方法で煤払いを行う神社や寺院などでは、新しく切り出した笹竹の先に葉や藁(わら)をつけた「煤梵天(すすぼんでん)」と呼ばれる掃除道具を使った煤払いが行われています。これには、高いところの煤や埃を落とすだけでなく、お清めの意味も込められています。 使い終わった煤梵天は、すぐに捨てず大切に扱い、1月15日前後の小正月頃に行われる「左義長(さぎちょう)」や「どんど焼き」といったお焚き上げの行事で燃やす地域もあります。
お焚き上げについて解説している記事もございます。
◆お焚き上げとは?いつ行うの?意味やタイミングについて解説します
煤払い祝い
江戸時代には、煤払いが終わるとお祝いをしていたとご紹介しました。多くの地域ではこういった習慣は廃れて久しいですが、現在でも、煤払い後のお祝いとして、神様に「煤払い団子」をお供えしたり餅や団子を食べたりする風習が残る地域もあるようです。
煤払いにならった掃除の順番
年神様を迎えるための清めの儀式であった煤払いにならい、現代の大掃除でも、神様やご先祖様が祀られている神聖な場所や、神様が宿る場所から掃除するのが良いと言われています。
神様やご先祖様が祀られている場所といえば神棚や仏壇が思い浮かぶと思いますが、それに加えて、日本では昔から、生活の中心にある竈(かまど)が大切にされてきました。竈には、「荒神様(こうじんさま)」「竈神(かまどがみ、くどがみ)様」と呼ばれる神様が宿るとされ、煤払いでも念入りに掃除したと言われています。竈を使わなくなった現代でも台所にお札を貼る習わしや、正月三が日の間は煮炊きをせず、おせち料理を食べて竈の神様を休ませるといった伝統が残っています。
こうしたことから、現在の大掃除でもまず神棚や仏壇を清め、続いて竈の神様が宿るとされる台所を丁寧に掃除し、その後に各部屋の掃除を進めると良いと言われています。 また、現代では基本的に家の中に煤が溜まることはありませんが、埃も天井や家具の上など高いところに溜まります。そのため、古くからの知恵を生かして、天井や壁などの高いところから埃や汚れを落とし、最後に床を掃除するという「上から下へ」の手順で行うと良いようです。
煤払いに合わせて、お墓も大掃除しませんか?
年末には、お墓の大掃除とお墓参りを
1年の汚れを払い、新年の準備を始める煤払いの時期には、家の大掃除と合わせてお墓の大掃除をするのもおすすめです。 前述のように、煤払いは年神様となったご先祖様の霊をお迎えするための清めの行事であり、心身や身の回りを清浄にして新年を迎えるための大切な習わしです。
ですから、この時期にお墓をきれいに整えることは、煤払いの本来の意味にも通じると言えるでしょう。
きれいに整えられたお墓で新年を迎えれば、ご先祖様もきっと喜ばれるはずです。
また、一年間家族を見守ってくださったことへの感謝を伝え、丁寧にお墓掃除をして手を合わせることで、今まで以上にご先祖さまとのつながりを感じながら、年を越すことができるでしょう。
12月のお墓参りの注意点
12月は冷え込みも厳しくなり雪が積もる地域もありますので、くれぐれも無理はせず、お墓参りの際には防寒対策をしっかりとして足元に気をつけてお参りするようにしましょう。
また、年末の12月29日は「にじゅうく(二重苦)」と聞こえることから、12月31日の大晦日は前夜に準備をすることがお通夜を連想させることから、それぞれ縁起が悪いとも言われています。年末近くにお墓参りをする場合には、12月28日まで、もしくは30日に行うとようでしょう。
一部の霊園では、年末年始期間を休業としている場合もあるため、事前に確認をすると安心です。
年末のお墓掃除やお墓参りについては、こちらを合わせてご覧ください。
◆お正月にお墓参りをしてもいい?年末年始のお墓参りの考え方や注意点をご紹介
まとめ
日本に古くから伝わる「煤払い」の行事についてご紹介しました。
時代や生活スタイルの変化とともに、各家庭では、お祓いや清めの行事ではなく「大掃除」へとその意味合いが変わってきていますが、「暮らしを守ってくれた家や神様に感謝する」、「お正月を気持ちよく迎える」といった思いは、今も変わらず受け継がれています。
また、神社やお寺では伝統的な煤払いが今でも行われており、年や季節の節目に穢れや汚れを祓い、神仏やご先祖様との繋がりを感じながら過ごす文化が根付いているのを感じます。
徐々に寒くなる上に年末に向けて慌ただしさも増す12月ではありますが、新年を穏やかな気持ちで迎えるためにも、神棚や台所の掃除を少しずつ進める、近くの寺社などに足を運んで煤払いの行事に参加してみる、お墓や仏壇をきれいにして1年の感謝を伝えるなど、ご自身に合った形でお正月に向けての準備を始めてみてはいかがでしょうか。
冬のお墓参りにおすすめの花や、年末年始のお墓参り、心身を整えて新年を迎えるための習わしの一つである「除夜の鐘」についても解説している記事がございますので、ぜひご覧ください。