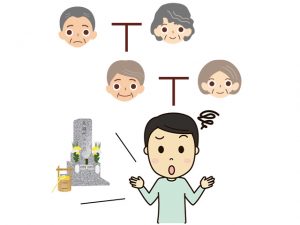お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
家族で考えたいお墓と税金〜お墓の生前購入と相続税対策〜

お墓は、人生の中でも重要な買い物の一つです。だからこそ、供養の気持ちや故人と家族の絆を形にすることだけでなく、購入のタイミングや、子や孫に負担がかからない方法などについても、じっくり考えたいものです。お墓を新しく建てる場合には、「贈与や相続にどれくらい費用がかかるのか?」「お墓を購入するのは、生前と死後のどちらが得になるのか?」「お墓を建てることが節税になると聞いたことがあるけど、実際にはどうなのか?」などの疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、お墓にかかる税金について、生前建墓は相続税対策になるのかどうかについてもあわせて、解説していきます。
お墓の購入や維持・管理にかかる税金
お墓を購入する際に必要な費用
お墓を新しく購入する場合、「墓石と工事の費用」の他に、墓地の「永代使用料」と「管理料」が必要になることが一般的です。墓地や霊園にお墓を建てる際、その土地自体を購入するのではなく、霊園や寺院から「墓地として使用する権利」を購入しますが、その費用が「永代使用料」です。また「管理費」は、施設のメンテナンスや運営のために霊園や墓地の管理者に支払う費用で、寺院の場合には、寺院の運営費も含めた「護持会費(ごじかいひ)」として請求されることもあります。
消費税がかかるもの、かからないもの
これらの中で、「墓石と工事の費用」、「墓地の管理料」には、消費税がかかります。一方で、「永代使用料」や「護持会費」については、宗教活動に関わるお金ということで非課税となり、消費税はかかりません。新しくお墓を建てた際に行う開眼法要や、回忌法要などで僧侶に支払うお金についても、同様に非課税とされています。
お墓と墓地の固定資産税は?
お墓には、固定資産税もかかりません。
まず、墓石については、「建てる」と表現することから建物と同じ扱いでは?と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、家屋ではないため固定資産税の対象にはなりません。
また、土地についても、墓地は固定資産税の対象とならないことが法律で定められており、さらに、お墓を建てる土地は基本的に墓地や霊園から借りている状態のため、固定資産税は発生しません。墓地や霊園のほか、墓地についての法律が作られる前から、山の中や田畑などの個人の敷地に建てられている「みなし墓地」の場合にも、基本的には固定資産税はかかりません。
お墓の相続・承継について
お墓は、分割できない「祭祀財産」
お墓は、民法において「祭祀財産」と呼ばれる財産の一つです。祭祀財産とは祖先を祀るために必要な財産のことで、お墓の他、先祖代々の系統を記載した家系図や過去帳、位牌や霊璽(れいじ)、仏壇や神棚などの祭壇や十字架、墓地の使用権や所有権などが含まれます。
これら祭祀財産は、預貯金や不動産など遺産分割に関わる「相続財産」とは区別されており、基本的には分割することができません。「祭祀承継者」と呼ばれる祖先の祭祀を催すべき人が、単独で承継することとなっており、もしその他の財産について相続放棄をした場合でも、「祭祀継承者」となり、生前に購入したお墓や仏壇などを引き継ぐことができます。
お墓の生前贈与はできない
お墓の承継については、祭祀承継者が亡くなったことによって引き継がれるのが基本となっています。また、一般的に、墓地の譲渡や転売は認められておらず、多くの墓地や霊園では、トラブル防止の観点から、生前贈与(生前の名義変更、生前承継)を禁止しています。
ただ、離婚や養子縁組、祭祀承継者が高齢や病気といった理由でその責任を果たすことができなくなった場合などは、例外として認められる場合もあるようです。
祭祀財産には相続税がかからない
祭祀財産の相続税については、相続税法第12条において、墓所、霊廟(れいびょう)及び祭具ならびにこれらに準ずるものは、相続税の課税価格に算入しないとされており、国税庁のホームページにある「タックスアンサー(よくある税の質問)」の「相続税がかからない財産」の項目には、相続税がかからない財産のうち祭祀に関わる主なものとして、「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。」と記されています。つまり、お墓をはじめとした祭祀財産には、基本的に相続税がかからないことが定められているのです。
お墓の持ち主が亡くなると、墓地の名義変更が必要になります。これには、数百円〜1万円程度の名義変更手数料が必要となることは覚えておくと良いでしょう。こちらも消費税はかかりません。寺院では「寄付金」扱いにしていることも多いようです。
お墓の生前購入が、相続税対策になる?
お墓の生前贈与は基本的にできませんが、前述のように相続税がかからないことから、生前にお墓や墓地などの祭祀財産を購入しておくことは、相続税の節税対策につながります。
例えば新しく墓石を購入する場合、大きさ、石質、細工などにもよりますが、一般的に工事費を含めて100万〜300万円ほどが相場だと言われています。また、墓地の永代使用料は、区画の大きさによって変わってくるため一概には言えませんが、全国平均で60万〜100万円ほどと言われています。ただし地域によっても相場が大きく違い、地価の高い東京近郊では平均100万〜200万円ほどになるようです。
故人が現預金を遺すと、家族が相続する際に相続税がかかってしまいます。しかし、生前にお墓を購入しておけば、課税対象となる現金を数百万円分減らすことができ、お墓も非課税で引き継げるため、相続税の節税につながるのです。
また、前述のように、お墓には固定資産税がかからず、税金として必要なのは、墓石の石材費や工事費、墓地の管理費それぞれにかかる消費税のみということになるため、総合的に見ても、お墓を生前に購入しておくことは、相続する家族の金銭的な負担軽減につながると言えるでしょう。
お墓を生前購入するメリット
「生きているうちからお墓を建てるのは縁起が悪いのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、仏教では生前墓のことを「寿陵(じゅりょう)」と呼び、「長寿」「子孫の繁栄」などを授かる縁起が良いものとする考え方があります。
また、生前にお墓を購入しておくとは、残された家族にかかる経済的な負担だけでなく、死後の手続きに追われ慌ただしく気持ちも落ち着かない中で、お墓を選んだり墓地を探したりするという、体力的、精神的な負担を軽減することに繋がります。その他、事前に家族とじっくり相談できることや、自分で墓地や霊園を見て周るなど、自分自身の意向を踏まえてお墓のデザインや場所を決められることもメリットと言えるでしょう。
お墓の生前購入で相続税対策をする際の注意点
ローン残額は相続税の対象になる
お墓などの祭祀財産は安いものではないため、ローンで購入を検討する方もいらっしゃるかもしれません。
通常、亡くなった方に債務(借金や未払金など)があった場合、それを遺産増額から差し引く「債務控除」をした上で相続税が計算されます。しかし、お墓や仏壇などの非課税の財産購入に関する未払いについては債務控除ができないため、もし所有者が亡くなった時点でローンが残っている場合には、ローン残高が相続税の対象となります。
相続税対策でお墓を購入するのであれば、現金一括購入にするなど、生前に支払いを終わらせておくことが大切です。
高額すぎる祭祀財産について
相続税が非課税になる祭祀財産の金額について、特に規定はありませんが、「日常礼拝をしているもの」というのが基本の考え方です。そのため、前述した国税庁のホームページの記載にもあるように、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや、「商品」として所有しているものについては、課税対象となってしまう場合があるため注意が必要です。
ペットの墓地の場合
お墓といえば、最近ではペット専用のお墓や霊園もありますが、日本の法律においてペットを含む動物は「モノ」とみなされ、祖先を祀るための祭祀財産の対象にならないため、相続税がかかります。
ただし、人間のお墓にペットが入る場合には、人間の墓地となるため、相続税は非課税となります。
ペットへの遺産相続につい的になる方はこちらをご覧ください。
◆ペットに財産を残せるの?〜ペットへの遺産相続について〜
その他の注意点
お墓を建てたら、まだ使用していないとしても、清掃などの管理が必要です。お墓掃除や草取りだけではなく、管理費も必要になることを覚えておきましょう。
また、墓地や霊園によっては、遺骨がある状態でないと申し込みができないところもあります。立地や金額だけではなく、申込の条件なども事前に確認しておくようにしましょう。
まとめ
購入や相続を含め、お墓のことというのは家族が何度も経験するようなことではない上に、何かと敬遠しがちな話題でもあるため、いざという時に慌てて決めなくてはならないということにもなりかねません。
まずは、自分の考えを家族に伝え、もし家族の意向と違ったり疑問が出てきたりした場合には、早めに調べたり話し合ったりしておくことが、納得のいくお墓の購入や承継、相続などの手続きにかかわる家族の負担軽減につながるのではないでしょうか。
家族に切り出しにくい話題だからこそ、終活の一環としてエンディングノートに自分の希望を書き出してみる、家族が集まっている時に話題にしてみるなど、お墓や相続に関わることをオープンにしていくことが大切と言えそうです。
お墓の相続や承継についての他の記事もあわせてお読みください。