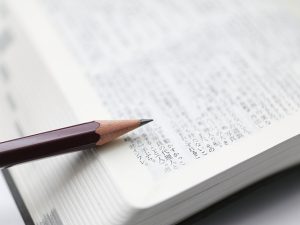お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
実は身近な仏教用語 たくあんの由来とは?語源になったと言われる沢庵宗彭について解説

朝食やお弁当の付け合わせなどの定番であるたくあん。ほどよい甘みとパリパリした歯ごたえがおいしいたくあんですが、お坊さんの名前が由来だという話を聞いたことはありませんか?
実は、普段よく使っている日本語の中には、仏教にゆかりのあるものが少なくありません。たくあんもその一つです。
たくあん漬けの由来になったと言われる沢庵(たくあん)和尚は、地位も名誉も求めず、波乱の人生を真摯に生きた人でした。
今回はたくあんの由来と、たくあんとの関わりが深い沢庵和尚こと沢庵宗彭(たくあん そうほう)の人生について解説します。
たくあんの由来とは?有名な説を紹介
たくあんという名前が定着した理由は諸説ありますが、沢庵宗彭と徳川家光の逸話から生まれたという説が有名です。
この説によると、江戸時代初期、徳川幕府の第3代将軍・徳川家光は普段から贅沢な食事を取っており「最近、何を食べてもおいしくない」と悩んでいました。そこで家光は、信頼している臨済宗の高僧、沢庵宗彭に何かおいしい食べ物はないかと相談します。
すると沢庵は、自分が住職を務める東海寺(とうかいじ)に、明日の午前中に来てほしいと言いました。
家光は約束通り翌日の午前中にお寺に到着しましたが、沢庵は家光を一度案内したあと姿を現さず、おいしい食べ物も出てきません。
家光は午後までひたすら待ち続けますが、だんだんお腹が空いてきました。そしてあまりの空腹に困り果てたころ、ようやく沢庵が現れ、ご飯と漬物だけの質素な食事を提供します。
お腹が空いていた家光は、質素な食事にもかかわらず、夢中で食べました。
そして食べ終わって満足した家光は、特に黄色の漬物を気に入り、沢庵に「この黄色い漬物は何か」と尋ねました。すると、沢庵は大根のぬか漬けだと答えます。
この大根のぬか漬けには特に名前が決まっていなかったため、家光が沢庵の名前をもとに「沢庵漬け」と名付けたと伝えられています。
ほかにも、保存食として「貯え(たくわえ)漬け」と呼ばれていたのが変化して「沢庵漬け」になった、沢庵の墓石が漬物石に似ていたから名付けられたといった説もあります。
いずれにしても、名前の由来になったと伝えられているくらい沢庵とたくあん漬けには深い関係があったと考えられるでしょう。
たくあんの由来となった沢庵はどんな人?
沢庵は実際に徳川家光と交流があり、困ったときに相談を受けるなど深く信頼されていました。しかし順風満帆のように思われる沢庵の人生は、実は波乱に満ちたものでした。
誕生から僧侶としての活躍
沢庵は安土桃山時代の始め頃の1573年、但馬国(たじまのくに)の出石(いずし、今の兵庫県豊岡市出石町)に生まれました。
10歳で出家してさまざまなお寺で修行の日々を送り、臨済宗の僧侶としてその名を知られるようになっていきます。
沢庵は権力や名誉、地位などを望まない僧侶で、教えを説くときもわかりやすい言葉で話すため、身分を問わず多くの人から人気がありました。また書や和歌、茶道などにも造詣が深く、文化人としても知られていたようです。
やがて京都にある、臨済宗大徳寺派の総本山・大徳寺(だいとくじ)の住持(じゅうじ、大規模なお寺の住職)になりますが、高い地位を望まず、あくまで一介の僧侶でいたいと願う彼は3日で住職をやめてしまったと言われています。
その後、沢庵は48歳のときに故郷の但馬にある宗鏡寺(すきょうじ)の近くに投淵軒(とうえんけん)という小さな住まいを構え、静かに暮らすようになりました。
ここでは「鶴亀の庭」や「心字の池」と呼ばれる美しい庭園の作庭をしたり、椿の木を植えたり、和歌を作ったりして過ごしていたと言われています。
宗鏡寺は沢庵との関係が深いお寺であることから沢庵寺と呼ばれ、今でも沢庵が伝えた製法でたくあん作りが行われています。
こうして静かな日々を過ごす沢庵でしたが、紫衣事件(しえじけん)により人生が一変します。
紫衣事件により流罪へ
1627年、徳川幕府と朝廷が対立した紫衣事件が起きます。
幕府は1615年に禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)を出し、さまざまな決まりごとを作ることで朝廷を統制しようとしていました。
この中に、高僧だけが着られる紫色の衣、紫衣(しえ)の着用には幕府の許可が必要という規定が盛り込まれていたことが事件のもととなります。もともと紫衣の着用は天皇が許可するものだったにもかかわらず、幕府の許可が必要とされてしまったのです。
しかし当時の天皇・後水尾天皇(ごみずのおてんのう)は、幕府の許可を得ずに紫衣の着用を許可していました。このことが幕府に問題視されます。
沢庵はほかの僧侶たちとともに幕府に抗議しますが、この行動がもととなり罪に問われ、流罪に処されてしまいます。
上山での生活
1629年、沢庵は上山藩(かみのやまはん、今の山形県上山市)へ流罪となります。流罪といっても、藩主からは住まいを提供され、大切に迎えられたようです。
沢庵のもとには農民たちから多くの大根が届けられたため、食べ切れない大根は「貯え漬け」にして保存したと言われています。また貯え漬けの作り方を一般の人にも伝えたことから、山形県上山市はたくあん発祥の地として知られるようになりました。
上山市には沢庵が住んだ春雨庵(はるさめあん)が復元されており、県指定の文化財となっています。
家光との交流
上山へ流罪となってから3年後、徳川家光の父で先代の将軍・徳川秀忠の死による恩赦で沢庵の罪は許されます。
沢庵は京都に戻ろうとしますが、すぐには許可されず、一旦江戸に立ち寄ります。ここで意外な縁から徳川家光に信頼される存在になりました。
実は沢庵は、柳生新陰流を生み出した剣豪、柳生宗矩(やぎゅうむねのり)と親しくしており、沢庵が説いた剣禅一如(けんぜんいちにょ、剣も禅も雑念を払い無になるという境地は同じ)の精神が宗矩の剣術に影響を与えたとも言われています。
そんな宗矩の勧めで、沢庵は家光と面会することになります。沢庵の人柄に感服した家光は、沢庵に帰依すると決め、品川に東海寺を開いて沢庵に住職を務めさせることにしました。
この東海寺が「たくあんの由来とは?」の項目でも解説した、沢庵と家光の逸話の舞台となります。 この逸話では沢庵が家光をいつまでも待たせるという奇妙な行動を取っていますが、これは「贅沢な食事に慣れてしまっているから、おいしい食べ物がないと感じてしまう。空腹になってから食事をするようにすれば食べ物をおいしく食べられる」ということを伝えたかったという意味があります。
沢庵の最期と遺言
1645年、沢庵は73歳のとき東海寺にて亡くなりました。
弟子たちに頼まれ、最後に「夢」という一文字を書き、「すべては夢であり無である」と言い残したと伝えられています。
さらに、葬儀や法事はいらない、死後の名誉も必要ないなどの遺言を残しており、最後まで名声などを求めない一介の僧侶としての生き方を貫きました。
沢庵のお墓はどこにある?
沢庵のお墓は、かつて住職を務めた東海寺の大山墓地にあります。
漬物石のような丸みのある自然石を乗せた形が特徴的で、国指定文化財になっています。
また故郷の出石にある、宗鏡寺の境内にも沢庵和尚塔所と呼ばれるお墓があります。
まとめ
たくあん漬けという名前が生まれ広まるまでには、沢庵の名誉を求めない生き方や、その生き方に魅せられたたくさんの人々との交流がありました。
沢庵と家光の逸話は、豪華な食事を食べられるという物質的な豊かさよりも、質素でも空腹を満たしてくれる食事のありがたみを知ることの大切さを教えてくれます。
いつでもおいしいものを食べられる現代だからこそ、食事の際には沢庵和尚のことを思い出し、食べ物やその生産に関わるすべての人への感謝を胸に「いただきます」と声に出してみてはいかがでしょうか。
沢庵が学んだ臨済宗は、座禅を重視する禅宗の一つです。
座禅は自分の中にある雑念を捨て、心を無にすることを目指す修行です。
現代では全国各地のお寺で座禅の体験会が開かれているため、忙しい日々の中で気持ちを落ち着けたり、ゆっくり自分と向き合ったりする時間がほしいと思ったら座禅に挑戦してみるのもおすすめです。
座禅の詳細についてはこちらをご覧ください。
また写経体験や宿坊体験も、日常から離れてリラックスするきっかけになります。あわせてチェックしてみてください。
写経については下記の記事で詳しく解説しています。
宿坊に泊まって座禅や写経にじっくり取り組むのもよいでしょう。