お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
立飯(たちは)・出立ちの膳って何?◆葬儀前に食事をとる意味、地域による違い、マナーを紹介◆
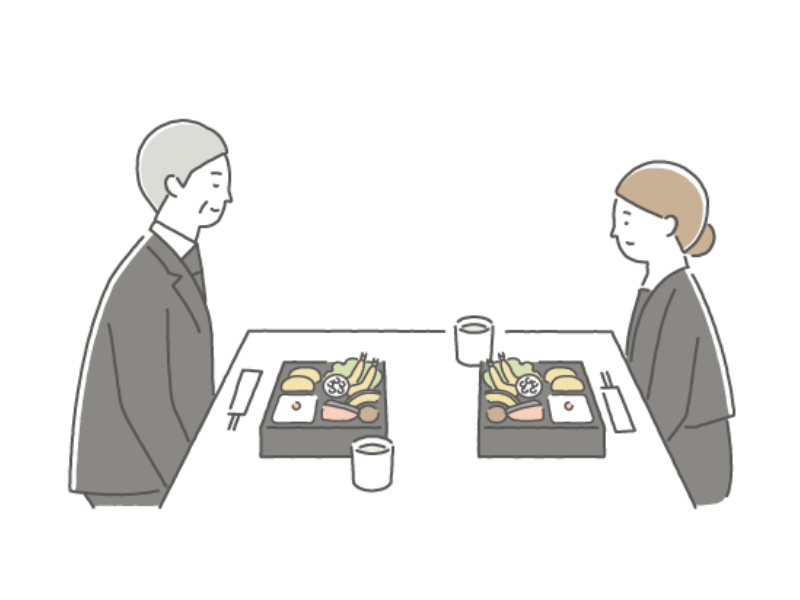
葬儀前や出棺前に故人と共に食事をする「立飯(たちは・たちはん)」「出立ちの膳(いでたちのぜん)」と呼ばれる風習をご存知でしょうか。「初めて聞いた」という方、また、実際にそうした場に立ち会ったことがあっても、「どんな意味があるの?」「何を食べるの?」「地域によって違うの?」など、詳しくは知らないという方も多いかもしれません。
今回は、立飯(出立ちの膳)とは何か?その意味や由来、地域による違い、行う際の流れや参列のマナーについて、この風習に込められた想いとともにご紹介します。
「立飯」「出立ちの膳」って何?込められた意味と由来
「立飯」「出立ちの膳」とは?
「立飯(たちは・たちはん)」・「出立ちの膳(いでたちのぜん)」とは、“故人との最後の食事”、“旅立ちのご飯”として、葬儀当日、葬儀や出棺の前に参列者にふるまわれる食事や、その食事会のことを指します。
葬儀に関わる食事としてよく知られている、通夜の後の「通夜振る舞い」や、葬儀の後の「精進落とし」に比べると、馴染みのない方が多いかもしれません。しかし、愛知県をはじめ、岡山県・広島県・山口県などの中国地方の一部地域、また、福岡県・大分県・宮崎県・鹿児島県といった九州の一部地域などでは、故人を偲ぶだけでなく、参列者への感謝や労いの気持ちを表す風習として、今も大切に受け継がれています。
宗派や地域によっては、実際に食事をとるのではなく、式の中で喪主や僧侶が食べるしぐさだけを行う場合もあるようです。 通夜振る舞い、精進落としについてもご紹介しています。
語源や由来
「立飯」という言葉は、かつての葬儀では参列者の人数が多く、立ったまま食事をとっていたことに由来すると言われています。「たちは」「たちはん」のほか、「たちめし」「りっぱん」と呼ぶ地域もあるようです。 また、もともとは、葬列を組んで火葬場や埋葬地へと向かう「野辺送り」に備えて、参列者が腹ごしらえをするための食事だったとも言われており、そうした背景からか、「出立ちの膳(いでたちのぜん)」とも呼ばれています。そのほか、地域によっては「出立ての膳(でたてのぜん)」「出立て(でたて)」「別れ飯」「お斎(おとき)」などとも呼ばれています。
どんな料理を、いつ食べる?
料理の内容
立飯(出立ちの膳)では、基本的には、肉や魚など動物性の食材を使わない「精進料理」が振る舞われます。これは、仏教における、殺生をしてはいけないという教えによるものです。
ただ、料理の内容については地域による違いも大きく、偲ぶ気持ちを表す意味で故人の好物や郷土料理が用意されることもあります。
地域のつながりの中、自宅などで葬儀が行われていた時代には、地域住民が手伝って食事を用意していましたが、現在では、葬儀社が提供する食事サービスや、仕出し弁当などを利用することがほとんどです。 精進料理については、こちらで詳しく解説しています。
行うタイミングと流れ
「故人との最後の食事」とされることから、出棺前に振る舞うのが基本の考え方ですが、現在では、葬儀当日の朝、通夜から付き添った親族や、通夜に続いて翌日の葬儀にも参列する方々に朝食として振る舞われるのが一般的です。 葬儀開式の1〜2時間ほど前に葬儀会場に集まり、食事をいただくのが通例で、一同に集まる場合もあれば、会場に入った方から順次いただく形式をとる場合もあります。地域によっては、出棺の前に行う場合もあります。
自宅で葬儀を行っていた時代には、立飯(出立ちの膳)の後、出棺の際に、藁を炊いて送り火をしたり、故人が愛用していた茶碗を割ったりする地域もあったようです。茶碗割りには、故人の魂が戻ってきたり未練を残したりしないようにとの意味が込められており、現在でも、故人を自宅に安置した後に葬儀場へ向かう際や、火葬場へ向かう出棺の際に霊柩車のクラクションに合わせて茶碗を割るなど、この風習が受け継がれている地域もあります。
地域で異なる立飯(出立ちの膳)の風習
愛知県西部(尾張地方)・三重県〜「涙汁」とは?〜
名古屋市をはじめとする愛知県西部(尾張地方)や、愛知県に隣接する三重県の桑名市などでは、出立ちの膳の際に、「涙汁」という胡椒(こしょう)や唐辛子を加えた辛い汁物を振る舞う風習があります。その素材から「胡椒汁」「唐辛子汁」とも呼ばれ、辛さで哀悼の涙を流しやすくするとともに、辛味によって疲れを癒すという意味があると言われています。
岡山県・広島県東部・山口県〜「たちは」と精進料理の形〜
岡山県や、隣接する広島県東部、そして山口県などでは、「立飯(たちは)」という呼び方が一般的です。
岡山県では、魚や肉を使わない巻き寿司や、稲荷寿司と巻き寿司を詰め合わせた「助六寿司」が振る舞われることが多く、広島県では、白いご飯に煮しめや味噌汁といった精進料理がよく見られます。現在では、近親者以外の会葬者には食事の代わりに会葬お礼の品(お茶やハンカチなど)を渡すことも多いようで、このお礼の品を「たちは」と呼び、「たちは」と書いた礼状を入れる地域もあります。
山口県の場合は少し異なり、出棺前に棺を囲んで精進料理をいただくという風習があるようです。その際、大豆やご飯のおこげを食べる地域もあります。山口県には、故人が旅立つ力をつけられるようにと、棺の中に大豆や米を納める地域もありますが、立飯で大豆やおこげを食べる意味については、よく分かっていないようです。
九州地方〜地域ごとの呼び名や習慣〜
福岡県や大分県では、一般に葬儀や法要の後に行われる食事会を指す「お斎(おとき)」という言葉を、葬儀前に行う出立ちの膳にも用いています。「お別れ膳」ともい言うようです。
また、宮崎県では「出立て(でたて)」、鹿児島県では「別れ飯」と呼ばれるなど、各地で独自の呼び名が残されています。
大分県の一部地域では、出棺の際に団子を配る風習がありますが、これも「出立ちの膳」の名残とされているようです。
立飯(出立ちの膳)を行う時の準備と流れ
葬儀社・寺院との相談
立飯(出立ちの膳)を行う場合、まずは葬儀社の担当者と綿密に打ち合わせを行い、葬儀の形式に合わせて、予算や料理の内容、どの範囲の方に振る舞うかなどを相談します。昔ながらの作法や地域の習わしを重んじる地域もありますので、親族とも相談しながら決めていくとよいでしょう。
また、宗派や寺院によっては、読経中に僧侶や喪主が食べる仕草をするなど、葬儀中の儀式の一部として行われることがあります。事前の準備が必要なこともありますので、寺院への相談や確認も忘れないようにしましょう。
人数把握と早めの案内
喪主は、葬儀前日までに人数と食事の準備数を確定し、手配を済ませる必要があります。参列者のうち誰に振る舞うのかは、式の規模や形式によって異なりますが、事前に親族に確認をとったり、参列予定者に参加の可否を尋ねたりして、食事が足りなくなることのないよう注意しましょう。
また、立飯(出立ちの膳)は葬儀の開式前に行うのが一般的です。開式時間に合わせて来場した場合、食事の時間が取れなくなることもありますので、参列者には、立飯(出立ちの膳)の実施と来場時間について、事前にきちんと案内しておくことが大切です。
なお、葬儀後に「精進落とし」の席を設ける場合には、そちらの食事数も同時に確認しておくと、準備や案内がスムーズになります。
参列する時のマナー〜服装・時間・食事〜
立飯の後にそのまま葬儀に参列するのが一般的な流れですので、服装は葬儀と同じく喪服を着用し、葬儀当日のマナーに準じるようにしましょう。
また、スケジュールには余裕がある場合が多いとはいえ、葬儀の進行を妨げないよう、主催者からの案内をよく確認し、早めに行動することが大切です。
食事中は、故人との最後の食事であることを意識し、静かに落ち着いた雰囲気でいただくとともに、故人との思い出を語ったり、遺族へのねぎらいや感謝の言葉を交わしたりと、場にふさわしい話題を心がけましょう。
食事が終わったら、席を整えてから立ち上がり、準備してくださった方々への感謝を伝えることも忘れないようにしましょう。
葬儀に関するマナーについては、こちらで詳しく解説しています。
◆通夜や葬儀の場にふさわしいお悔やみの言葉とは〜マナーやNGワードを紹介〜
まとめ
立飯(出立ちの膳)をはじめ、葬儀の場で食事を囲む風習には、故人を偲び、感謝を伝え、悲しみを分かち合うという大切な意味が込められています。
葬儀のかたちが変わりつつある今も、こうした風習が各地で受け継がれているのは、心を尽くして故人を送りたい、つながりのある人たちと共に想いを交わしたいという願いのあらわれなのかもしれません。
食事は、人と人との心の距離を自然と近づけてくれるものです。共に過ごすひとときが、遺された人たちにとって、これからを歩む心の支えになることもあるでしょう。
これを機会に、家族と一緒に、お互いの気持ちを大切にできる葬儀やその後の供養のあり方を考えてみてはいかがでしょうか?
生前に自分自身のお墓を用意する人も増えています。下記の記事でメリットについても解説しています。葬儀や、お墓参りのあり方についてまとめた、記事もありますので、合わせてお読みください。










