お役立ちコラム お墓の色々
お役立ちコラム お墓の色々
- 供養をきわめる -
神道ではお盆をどう過ごす?〜そこに込められた意味や仏教との違いを解説〜
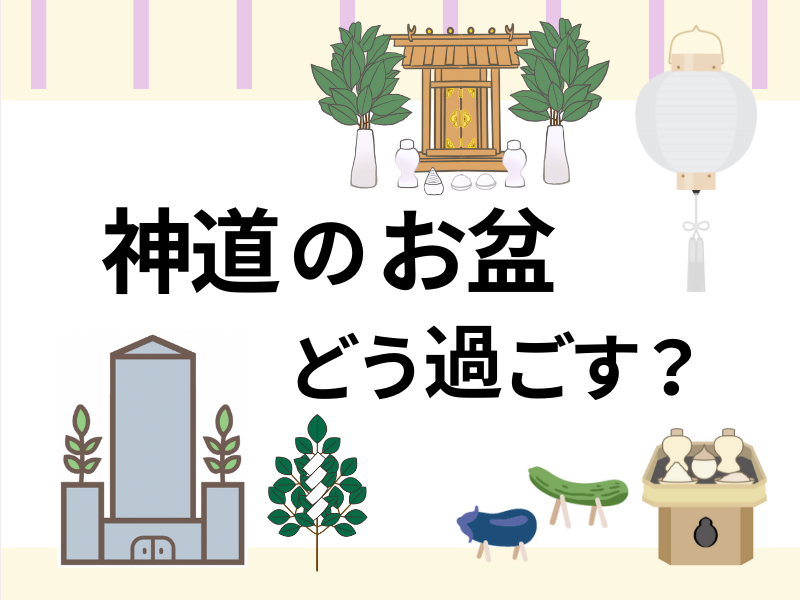
お盆は、日本で昔から大切にされてきた伝統文化です。一般的には、ご先祖様を供養する仏教行事として定着していますが、神道では、どのようにお盆を過ごすのでしょうか?
その歴史を辿ると、日本に古くからある信仰や風習にもルーツがあると言われている「お盆」。今回は、神道におけるお盆の過ごし方を中心に、行事に込められた意味や、迎え火や送り火、お墓参りなどの習わしについて、仏教との共通点や違いにも触れながら解説します。
神道にお盆はあるの?
お盆とは、ご先祖様の霊(精霊/しょうりょう)を自宅にお迎えし、感謝を込めて丁寧にもてなし、再び送り出す、日本の夏を代表する伝統行事です。
一般的には、故人やご先祖様の供養というイメージが強く、仏教の行事だと思われがちですが、実は日本古来の祖霊信仰とも深い関わりがあり、神道においても、ご先祖様の御霊(みたま)をお祀りする大切な行事の一つとされています。
お盆の成り立ち
お盆の起源は、中国から伝わった、ご先祖様にお供えをして供養するという仏教行事「盂蘭盆会(うらぼんえ)」にあるとする説が広く知られています。
一方、日本には古くから、神道のルーツとも言われる、自然やご先祖様の霊(祖霊)を敬う自然崇拝や祖霊信仰が生活の中に溶け込んでいました。故人やご先祖様の御霊は年月を経て昇華されて、やがて祖霊となって土地や子孫を見守る「守り神」のような存在になる。このような考え方のもと、祖霊を家に招いてもてなす風習があったと言われています。
こうした日本固有の信仰や風習と、のちに伝来した盂蘭盆会の行事や仏教の教えが混ざり合いながら、現在の「お盆」の行事が形作られていったと考えられています。
さらに詳しいお盆の起源や由来については、こちらの記事で解説しています。
神道におけるお盆の意味
仏教では、「故人やご先祖様の精霊を慰め、感謝を伝え冥福を祈る」「供養を通じて功徳を積む」といった意味合いのもと、地域や各家庭で様々な行事が行われるお盆。
神道でも同様に、さまざまな行事が行われますが、その行事には、「家族や土地を見守ってくれている祖霊に感謝を伝え、丁寧にもてなし、御霊の安寧を祈る」といった意味が込められています。また、「一年間、家族が無事に過ごせたことや、家族の健康と長寿を祝う」という意味合いもあり、こうした点は神道らしい特徴と言えるでしょう。
神道のお盆の過ごし方、仏教と共通点や違いは?
それでは、神道における実際のお盆の迎え方を、仏教との違いも交えながら見ていきましょう。
故人が亡くなって初めてのお盆「初盆祭」「新御霊祭」
故人が亡くなってから初めて迎えるお盆は、初めて自宅に戻ってくる故人の御霊が迷わないようにと、普段よりも丁寧に供養やお祀りをする習わしがあります。
仏教では、この日を「初盆(はつぼん)」「新盆(にいぼん・あらぼん・しんぼん)」と呼び、僧侶を迎えて読経してもらうなどの法要を行うのが一般的です。
一方、神道では、「初盆祭」や「新御霊祭(あらみたまさい)」と呼び、神主を迎えて祝詞(のりと)の奏上をしてもらうなどの儀式を行います。仏教では四十九日を過ぎて初めて迎えるお盆を指すのに対し、神道では、「故人が亡くなった日から1年以内に迎えるお盆」を指す点にも違いがあります。
この時には、「白提灯」「白紋天(しろもんてん)」と呼ばれる白い提灯を玄関先などに飾る風習もありますが、神道の場合、仏教のように蓮や菊の花などの白い透かし模様が入ったものではなく、白無地の提灯を使うことが基本となっています。
仏教の初盆・新盆については、こちらの記事で紹介しています。
迎え火・送り火
神道でも仏教と同じように、13日の夕方に迎え火を、16日(または15日)の夕方に送り火を焚く習わしがあります。祖霊が迷わないための目印となるだけでなく、立ち上る煙に乗って、ご先祖様が行き来すると考えられています。
火を灯す際は、麻の茎を乾燥させた「おがら」や、松を細かく割った「松明(たいまつ)」を使います。特に麻は、古くか穢れを清める力あると信じられており、現在でも神社や神事において欠かせない存在です。浄化作用のある麻を焚くことで、空間を清め、先祖様を迎え入れる準備を整えるという意味も込められています。
お墓掃除とお墓参り
お墓を掃除し、整えた上でお参りすることは、仏教でも神道でも共通するお盆の大切な習わしです。ローソクを灯し、お供え物をすることは仏教と共通していますが、そのお供え物の内容やお参りの仕方に特徴があるため、簡単にご紹介します。
花立てには「榊(さかき)」
神道では、花立てに、花ではなく「榊(さかき)」の枝葉をお供えします。仏教で用いられる「樒(しきみ・しきび)」と似ていますが、別の植物です。榊は、神道において「神が宿る依り代(よりしろ)」となる神聖な植物とされ、神様と私たちの世界を繋ぐ役割をもつと考えられています。
ただ近年では、菊や百合、カスミソウなど、白い花を中心に故人が好きだった花をお供えすることもあるようです。
それぞれの違いや込められている意味については、こちらの記事もお読みください。
◆樒(しきみ・しきび)と榊(さかき)の違い〜樒をお供えする意味や使われ方を紹介します〜
神様へのお供え物「神饌(しんせん)」
仏教でお供えする食べ物は、果物やお菓子などを中心に、故人が生前好きだったものが基本とされています。ただし、殺生を避けるという教えから、肉や魚など動物性のものはタブーとされています。
一方、神道におけるお供物は、「神饌(しんせん)」と呼ばれ、米、酒、塩、水、餅、旬の魚介類・野菜・果物、お菓子などがこれにあたりますが、お墓参りの際にはこの中から、洗米、お神酒、塩、水をお供えするのが基本とされています。
お供え物の違いについては、こちらでも詳しく解説しています。
◆お墓参りのお供え物、宗教や宗派で違う? 正しい供え方と墓石を守るマナー
線香ではなく「玉串(たまぐし)」
神道には、仏教のように線香や焼香を焚くという習わしはなく、神前には「玉串(たまぐし)」をお供えします。玉串とは、榊(さかき)の枝葉に、「紙垂(しで)」と呼ばれる白い紙(しめ縄などにも付けられる、稲妻のように形作られた紙)を付けたものです。
線香が、浄化や、あの世とこの世を繋ぐといった役割で用いられるように、玉串も、穢れを祓い清め、神様と人とを仲立ちするものとして用いられています。
仏教における線香の意味については、こちらで解説しています。
「二礼二拍手一礼」
墓前で手を合わせる際は、「二礼二拍手一礼」という神道の基本的な作法に従います。これは、神様への敬意と感謝を示す作法であり、てのひらを打ち合わせて鳴らす「拍手(はくしゅ・かしわで)には、神様を招き、その場所や心身を清めるといった意味があると言われています。
ただし、故人が亡くなり五十日祭を迎えるまでは、拍手の際に音を立てないようにします。
神道のお墓参りの、より詳しい作法やマナーについては、こちらの記事で解説しています。
神徒壇(祖霊舎)の掃除・盆棚の飾り付けとお供え
神道では、神棚とは別に、仏教における仏壇に相当し、祖霊をお祀りする「神徒壇(しんとだん)」「祖霊舎(それいしゃ)」と呼ばれる祭壇があります。ここを丁寧に掃除し、「盆棚」と呼ばれる特別な祭壇を準備するのも、仏教と共通の習わしです。
盆棚には、仏教における位牌にあたる「霊璽(れいじ)」をお祀りし、榊と神饌をお供えして祖霊をお迎えします。夏の野菜や果物、お菓子、お頭付きの魚などをお供えすることもあり、ナスやキュウリで作った精霊馬・精霊牛を飾る地域もあります。
盆棚の両脇や玄関、軒先などに、盆提灯や灯籠を飾る習わしも、仏教と共通しています。
仏教における盆棚の基本的な飾り方などについては、こちらで解説しています。
◆お盆飾りの精霊棚(盆棚)とは?飾る時期・必要なもの・一般的な飾り方まであわせて解説
地域の行事
お盆の時期には、全国各地で、迎え火や送り火、盆踊りなどの行事が開催されており、こうした行事に参加することも、昔からのお盆の過ごし方の一つです。
日本では、仏教の普及に伴って、亡くなった人の弔いや供養をお寺が担っていた歴史があり、仏教との関わりが深い行事も少なくありませんが、一方で、神事が元になった祭りや、特定の宗教とは直接結びつかず、古くからの信仰や文化、暮らしの中で生まれ、受け継がれてきた行事も数多くあり、これらのお盆の行事は、宗教や宗派を問わず、多くの人がご先祖さまを想いながら参加する、「地域行事」として根付いています。
お盆に由来する行事については、こちらの記事もご覧ください。
◆大阪・関西万博でも開催?全国のお盆の行事を紹介(盆踊り編)
◆五山送り火やねぶた祭りも!全国のお盆の行事を紹介(迎え火・送り火編)
まとめ〜受け継がれてきたご先祖様への感謝の心〜
神道における、お盆の意味や過ごし方について、仏教との違いにも触れながらご紹介してきました。
お盆の迎え方や習わしについては、一部に作法の違いはあるものの、迎え火や送り火、お墓参り、盆棚の飾りやお供えなど、基本の流れは仏教とよく似ています。その重なりの中には、仏教と神道それぞれの立場から大切にされてきた、「ご先祖様への感謝を伝える」という共通の想いや、日本の文化の中で息づいてきた祈りの形が感じられます。
また神道には、ご先祖様は成仏して遠くへ行ってしまう存在ではなく、今もどこかで見守ってくださる「守り神」のような存在とする考え方が古くから受け継がれています。そのような、ご先祖様との距離感や関わり方からも、日本の「お盆」の源流を感じることができるでしょう。
お墓参りという習慣もまた、世代を超えて受け継がれてきた、日本人ならではの祈りの形の一つです。今年のお盆は、家族そろってお墓の前に手を合わせ、ご先祖様の存在や、家族の絆をあらためて感じるひとときにしてみてはいかがでしょうか。
お盆の起源や一般的な風習などについてまとめた記事、神道のお墓について詳しく解説している記事もございますので、合わせてお読みください。








